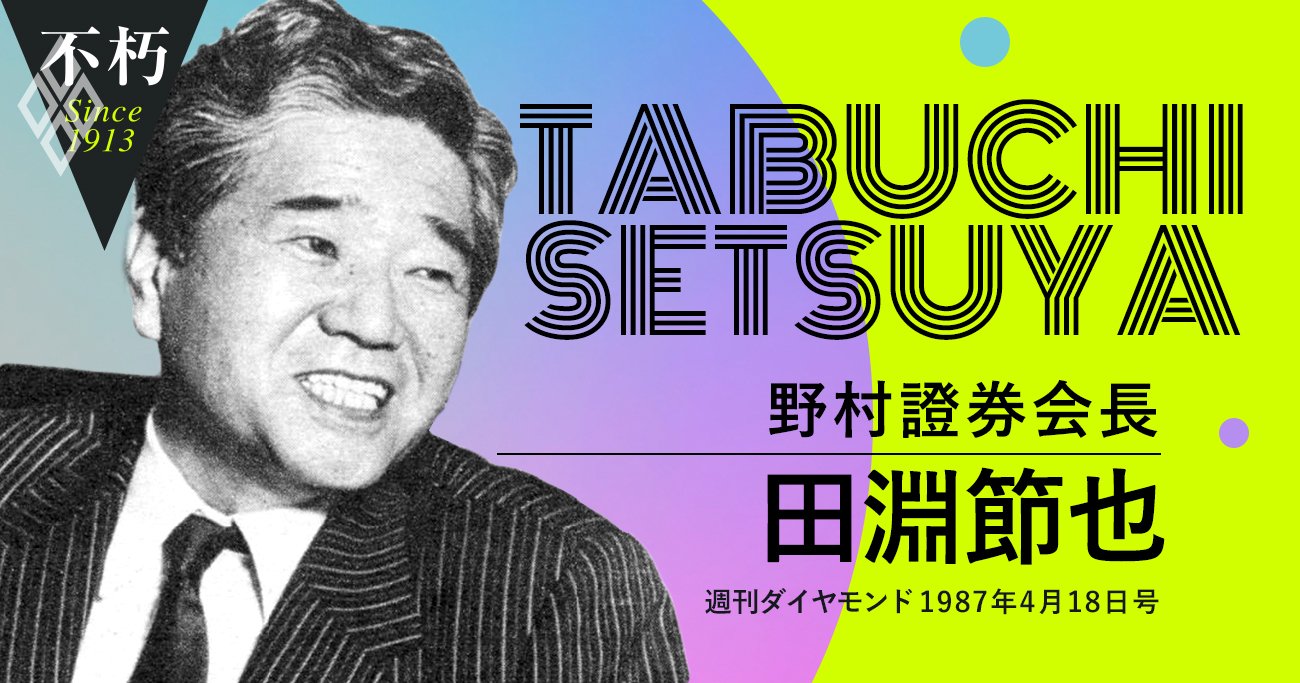
田淵は終戦後の1947年に野村證券に入社。奥村綱雄、瀬川美能留、北裏喜一郎という歴代名物社長の下、主に営業畑で活躍した。「ノルマ証券」の異名を取る「稼げない男は無価値」という社風の中で出世街道を駆け上がり、40歳で取締役となり、78年に54歳の若さで社長に就任した。
そして、国内営業体制を固めつつ、情報化戦略と国際戦略の三正面作戦を遂行。奥村、瀬川、北裏が進めてきた証券業の近代化、すなわち“株屋”から金融機関への転換を完成させ、87年9月期決算では経常利益で日本一になるなど、社長・会長を務めた13年間で野村證券を証券業界で群を抜く存在に仕立て上げた。経済同友会副代表幹事を務めた後、90年12月には日本経済団体連合会(経団連)で証券業界初の副会長となった。
聞き手の野田は、インタビュー後記(本記事には未掲載)で「田淵さんは、きまじめな農業技師と教員という共働き夫婦の下で小さいときから突出しないことを身に付けてきた。それは多数の側で上手に生きていくということであり、一方でその現実を享受する能力を持つ人でもある。大学では軍国主義にもマルクス主義にも染まらなかったし、戦後民主主義に感動したということもなく、あまり野心のあった人ではない」と分析している。
一方の田淵は、記事内で「史観」を持つことの重要性を説いている。「史観に基づいた基本がないと、表面的な変化、人まねをやって終わってしまう。それでは本当の変化ができない。だから、大げさに言うようだけれども、史観があれば一つの会社が1代でダメになる前にもっと見通せると思うんです」と言う。
この記事の後、バブル崩壊に伴い証券業界は激震に見舞われる。91年に発覚した特定の大口顧客への損失補填や、暴力団関係者との不透明な取引など一連の証券不祥事を機に、田淵は一線を退いた。その実力と人柄で、財界内からは復帰を望む声は多かったが、一切応えなかった。「私は、証券会社の歴史をつくった自負がある。一度歴史から降りた人間が、また登場して成功した例はない」と周囲に語っていたという。潔い引き際も、田淵なりの史観だったのだろう。(敬称略)(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)
証券会社は戦後資本主義の
“根っこ”になるという勘
 1987年4月18日号より
1987年4月18日号より
――田淵さんは、1923年に父の任地である韓国の大邱で生まれた。実家は島根県松江で小さな地主をしていたが、父親は農業技師、母親は小学校教員だった。中学4年までは大邱で過ごしたが、以後は旧制松江高校(現島根大学)を経て京都大学法学部に。
田舎の高校だから勉強もせずに、あまり試験の難しくない京都大学に入って、学校に入るや否や学徒徴令で海軍に取られて……。だから全く勉強せずだ。大体確たる目的のない人は法学部に行ったんだ(笑)。
軍に取られることについては、これはもう、やむを得んと思っていた。国のために尽くそうとか、ばかな戦争をしているとか、という気持ちもなかった。ただ、海軍に行って海は好きになったな。
――44年、海軍の予備学生として九州・大村湾の魚雷艇基地で、特攻兵器回天搭乗員の選抜があった。そのときに「熱望」「望」「否」のいずれかと聞かれて田淵さんは「望」と答えている。いつか死ぬのにあえて熱望することもないと、真ん中を取った。ファナティックになるのではなく、現実的な選択を常に取ってきた。
卒業の頃は、誠に具合が悪いときで、就職先はあんまりないし、三井物流へでも行きたいなと思ったんだけれども、財閥解体でなくなってしまった。なるべく現実的な仕事(人と人との付き合い)をやりたかった。じっと座って、というんじゃなくて。毎日毎日行動的な仕事をしたかった。
役人になるつもりはなかった。子供のときから好きじゃなかった。共産党に走ったり、そういう青年もいたけれど、やはり当時から、僕は常に全体の中であって、一部の中には加担しない。あくまで真ん中です。
もっとも奥村さん(戦後の野村證券中興の祖・奥村綱雄。当時京都支店長。友人の紹介で出会う)の影響が非常に僕は大きいんです。奥村さんがおまえは見どころがあるから野村へ来て、ひとつ思い切り働けと、そういう一言が効きました。そこでいろいろ考えたわけです。いまからの日本は資本主義でいくのだろう。資本主義でいくとしたら証券会社は、資本主義の中に深く組み込まれていて、根っこのようなものではないかと。少なくとも時代が落ち着いたら米国みたいになるだろうと漠然とした勘で思った。
銀行の方はあんまり行く気しなかったね。資本主義の中でも、あまりにも静的だから。株屋さんに勤めるという意識はなかったね。兜町には株屋さんはたくさんあるが、野村はわりに、当時から企業アイデンティティが確立されていました。日本にウォールストリートができるかどうかは別にして、ウォールストリート的な、株を通して産業社会が見えてくるという感じはあった。







