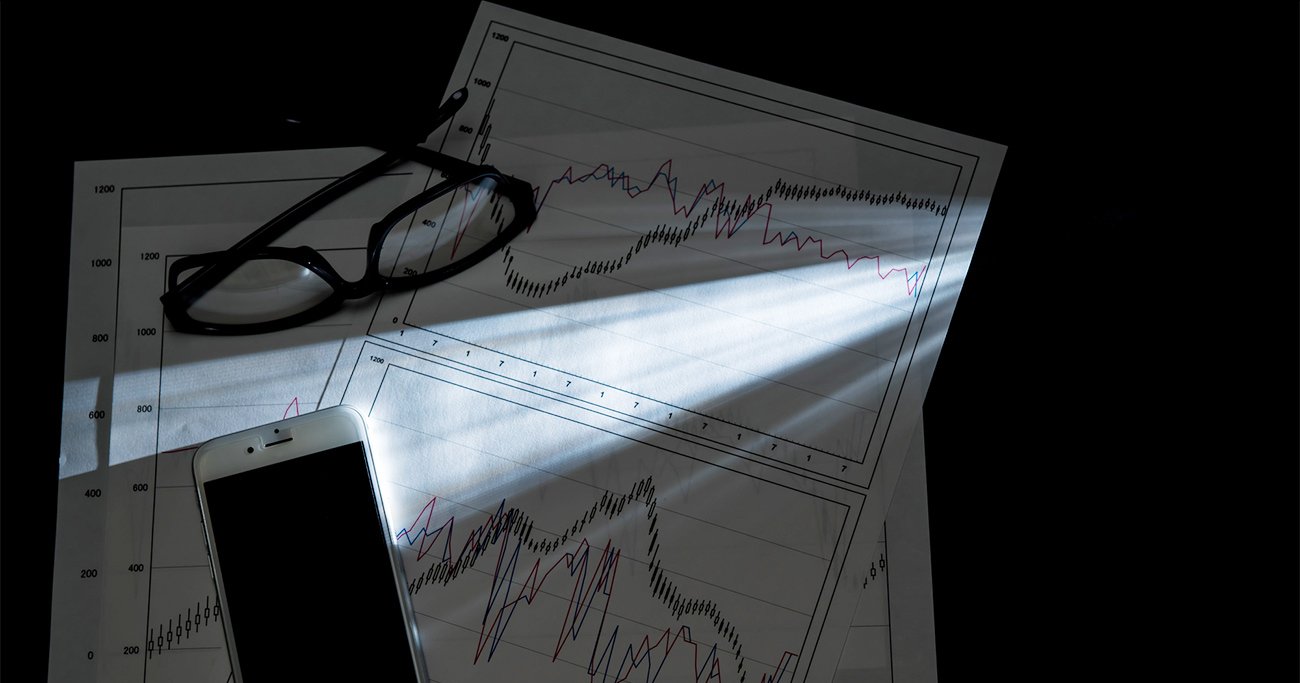 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
転職・退職が珍しくない証券業界において、新たな人材流出の流れが起きている。より顧客本位の業務を実践するIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)へ、転身する人材が増えているのだ。デジタル革命以後、旧態依然の証券業界が抱える問題を提起する。
退社を決断した理由
東京・大手町のカフェに時間通りに着くと、すでに二人の若者が待ち構えていた。きちんとした身なりで、さわやかな笑顔。それはあれこれと頭に浮かべた人物像のどれにも当てはまらないタイプだった。
この日、出会ったのは平行秀、松岡隼士の両氏である。大学の同じゼミで1年次違いの両氏は2011年、2012年に相次いで野村證券に入社。平氏は新宿野村ビル支店、松岡氏は横浜支店を振り出しに優秀な実績を上げ、その証として、平氏は海外修練生としてロンドンに派遣され、松岡氏は本社ソリューション・アンド・サポート部に異動した。将来を嘱望されている社員の典型的なエリートコースといえる。
ちなみに海外修練生は、優秀な営業実績を上げ続けた若手社員の中から選りすぐられた者にだけ与えられる、1年間の海外研修制度である。一般的な留学制度ではなく、自分の興味ある分野の知見を高めることを目的としている。一方、ソリューション・アンド・サポート部は全国の営業拠点で汗を流す営業社員たちを支援する本部セクションだ。やはり、すぐれた実績を築いて社内で高い評価を得なければ、その部署には配属されない。
したがって、2019年春、入社9年目の平氏と8年目の松岡氏が揃って辞表を提出するとは、おそらく社内の誰もが予想していなかったにちがいない。しかし、退職するまでの間、悩みを深めていた彼らは、しばしば電話で相談していた。当初は「野村をこういうようにつくり変えたいね」という会話だったが、次第にその内容は変わっていった。会社任せではなく、「自分たちの力で新たな証券ビジネスが生まれるプラットフォームをつくろう」と。
会社を変えるのではなく、「証券ビジネスの根幹を自分たちが変える」という、途方もない決断をしたのだ。
その出発点はどこにあったのか。実は「営業目標の達成はさほど難しいことではない」と言い切る彼らが、日々の営業活動の中で浮かんだ疑問からだった。それはきわめてベーシックであり、したがって、本質的な問題への疑問でもあった。
「私たちの職場では、なぜ、顧客が担当者を選べないのか」
「なぜ、私たちは職場で自分たちの転勤、キャリア、実績数字の話しかしないのか」
職場では「顧客が主語となるような会話はまったくなかった」と二人は振り返る。
IFA=証券リテール営業の新たな担い手
これは、言い得て妙なほどに、金融ビジネスのいまの病巣をえぐり出した表現と評していい。
近年、金融庁は「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)」を打ち出し、その和訳である「顧客本位の業務」を提唱していた。そんな概念的なニュアンスより、彼ら二人の言う「顧客が主語となって、顧客が選ぶ」のほうが、圧倒的にわかりやすくてリアリティがある。逆にいうと、
「証券会社が顧客を選び、顧客に何を買わせるか」
「顧客をどう誘導し投資させるのか」
という発想に未だ固執し続けているのが、証券業界の生々しい現実ということになる。
自社の事業計画に基づいて営業計画が策定され、それを達成すべく、本部から営業店、そして、営業店から個々の営業担当者へと「営業目標」が課されている。多くの場合、月次単位で細分化され、さらには週次、日次の営業成績が集計されて、最終ゴールまでのラップレコードの順位付けで営業担当者の尻叩きが行われる。
同じ金融ジャンルの中でも、とりわけ証券ビジネスでは厳しいノルマが業界風土のように定着していて、根性や人情をフル活用した、浪花節的なセールス活動を展開してきた。上司は「なんとか、顧客にはめてこい」と檄を飛ばし、担当者は「今日は何人の顧客に売り込みました」という表層的な会話が職場に充満する。確かに、そこには顧客を主語とする会話はない。「顧客」は「を」「に」が後につく目的語と化している。
そのような営業スタイルからの脱却を目指して模索する動きは、これまでまったくないわけではなかった。かの二人が在籍した野村證券も、前時代的な営業姿勢を改めようとしてきた一社である。実際、平均的に見れば、かつてほど顧客無視のセールスはひどくない。「問題を引き起こすようなセールスは厳禁」というルールを掲げる証券会社も現れてきていた。
だが、その一方で、株式の委託手数料、投信の募集・販売手数料で構成される営業目標は厳然として設定されている。その達成へのプレッシャーは、上司のチェックから始まり、人事評価にまで及んでいる。結局、顧客無視、軽視のセールスは会社が命じたわけではなく、あくまでも「営業社員が勝手にやり過ぎたことである」という体裁へと変わっただけに過ぎず、その内実はまったく変わらない。いわゆる「押し売りセールス」「お願いセールス」「おべっかセールス」であり、顧客からの不平、不満、苦情を誘発しやすいという意味では、以前と同様のままなのである。







