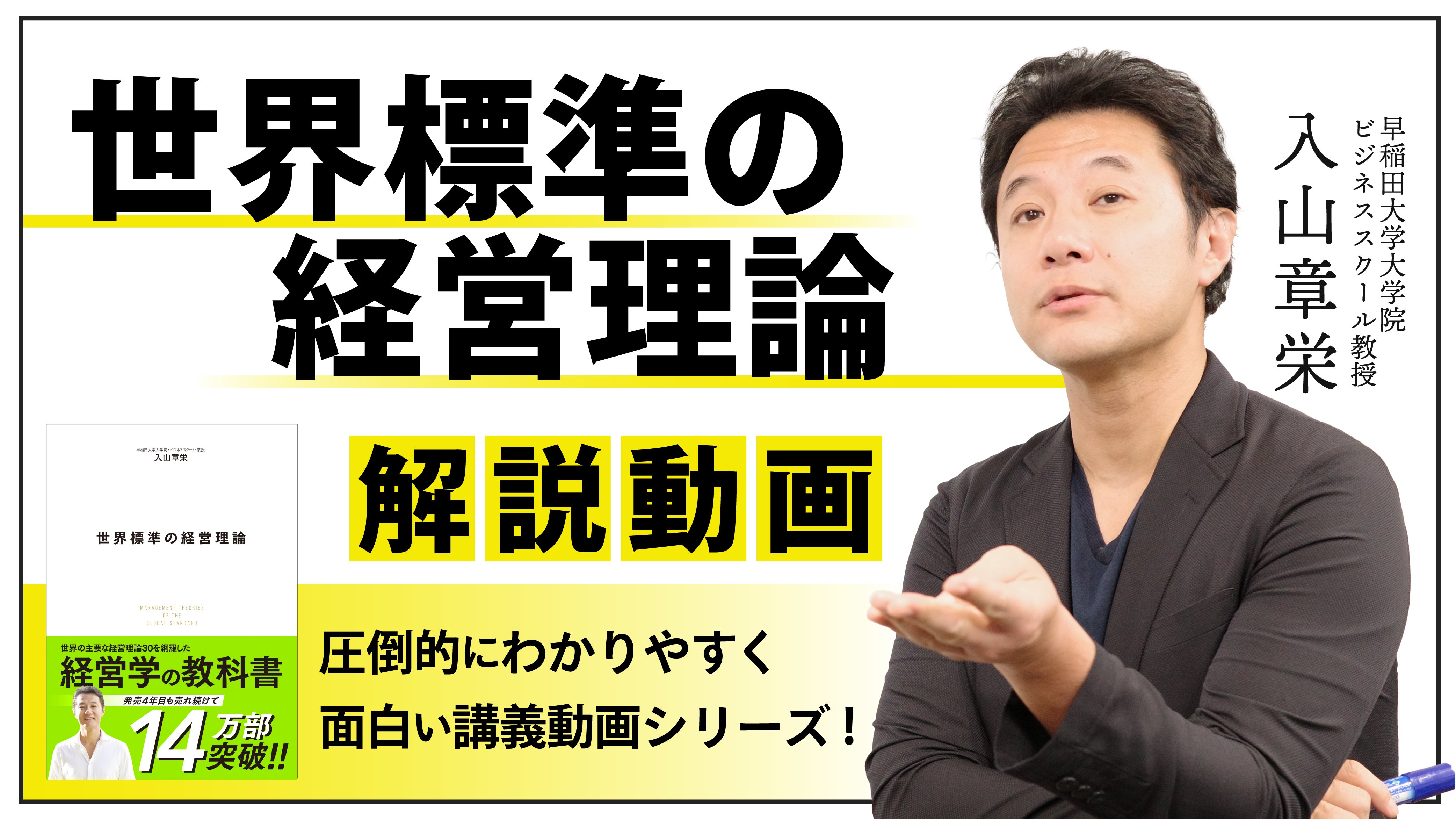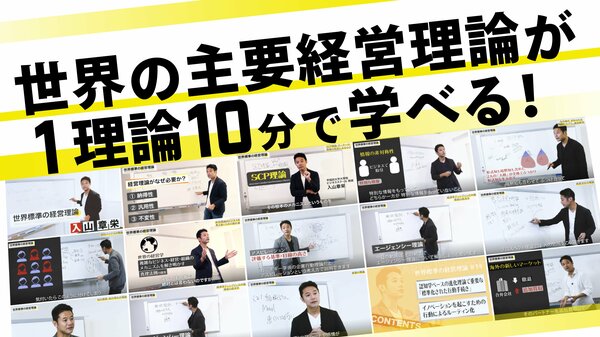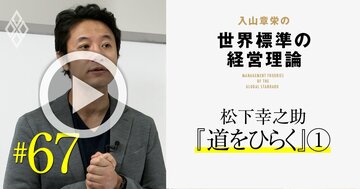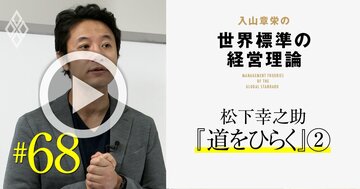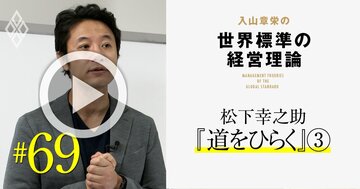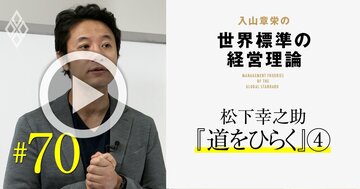「10パーセントの工夫」で
運命を変えた大企業とは?
しかし、『道をひらく』で「残りの10パーセントくらいが、人間の知恵、才覚によって左右される」と語られている通り、企業にも運命に抗う術はある。
例えば米デュポンは、もともとはダイナマイトや無煙火薬などの製造を手掛けていたが、時代の変化に応じて化学メーカーへと業態を転換した。独シーメンスも同様に、自動車部品や情報通信関連機器の製造から、エネルギー・工業部品・ヘルスケアなどへと主力事業を切り替えた。
米IBMも、1960~70年代に隆盛を極めた大型サーバー「メインフレーム」から、クラウドやAI(人工知能)へと主力事業を変えてきた。
ただ、これらは何も「オタマジャクシ→トカゲ」「出版社→自動車メーカー」というほどの突拍子もない変化ではない。
歴代の経営陣が「生態系(=市場環境)」の変化を先読みし、長期的なビジョンに基づいて、戦略的な投資と方針転換、事業再編などを行った結果である。その過程では、IBMのパソコン事業など外部に売却された事業もある。
もし旧態依然としたビジネスモデルのままであれば、各社はライバル企業に「捕食」されていたかもしれない。各社の経営陣は、その才覚によって自社の運命を変えた。いわば「道をひらいた」のである。
「市場環境を先読みし、勝つための投資や取捨選択を繰り返す」――。この思考作業の重要性が学べるからこそ、『道をひらく』は現代のビジネスに通じているといえる。
たとえ経営陣によって変えられる余地が「残りの10パーセントくらい」であっても、その積み重ねが後世での勝敗(=運命)を大きく左右するのだ。
いかがだっただろうか。「学びの動画」の特集『入山章栄の世界標準の経営理論』では、「組織エコロジー理論」以外の経営理論も紹介しながら、『道をひらく』が現代ビジネスに通じている点を詳しく解説している。本記事で興味を持った方は、ぜひチェックしてみてほしい。