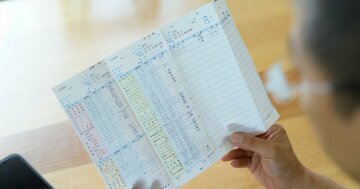肥満症とその予備軍の
脂肪を減らす最新治療とは?
では、肥満症と診断された場合には、どのような治療があるのだろうか。
「肥満症の治療の基本は、食事療法と運動を組み合わせて減量することです。体重の3%以上減量すると、血圧や中性脂肪、血糖値、LDLコレステロール、肝機能を表すAST、ALT、γGTP、尿酸値などが有意に改善することが日本人のデータで示されています。肥満症の人にとって3%以上の減量は、さまざまな健康障害を改善するために有用なのです」
BMI35以上の高度肥満で、食事療法や運動による減量、薬による治療で改善しない場合には、胃の一部を切除するスリーブ状胃切除を受ける選択肢がある。胃の一部を切り取って細長い筒のように小さくして、摂取エネルギーを減らす方法で、2015年に保険適応になった。対象は18~65歳、他の病気が原因ではない肥満症で、6カ月以上の内科治療で改善が見られないBMI35(糖尿病や脂質異常症等の代謝障害を合併する場合にはBMI32.5)以上の人だ。
例えば、千葉大学医学部附属病院でスリーブ状胃切除を受けた男性は、体重が120㎏の高度肥満症で、「いつ突然死してもおかしくない」と主治医に言われていたが、手術後は74㎏になり、健康障害も改善されたという。
しかし、手術は高度肥満症の人しか受けられず、日本では昨年の初めまでBMI35未満の肥満症に対して使える薬がなかった。そんな中、肥満症治療の新たな切り札として登場したのが、2023年3月に保険適用になった注射薬のセマグルチド(商品名・ウゴービ)だ。
糖尿病の治療薬のGLP-1受容体作動薬の用量を増やして肥満症の治療に応用した薬で、医師の処方で週1回注射する必要がある。食事療法・運動療法では十分な効果が得られないBMI27以上で健康障害が2つ以上ある人か、BMI35以上の高度肥満症の人が対象だ。
脳に働いて食欲と胃の働きを抑える効果があり、日本人を対象にした治験では、食事と運動習慣の見直しといった生活習慣の改善とともに投与することで、約10%以上の体重減少効果が報告されている。ただし、吐き気や嘔吐、下痢、便秘、食欲減退などの副作用が出る場合がある。