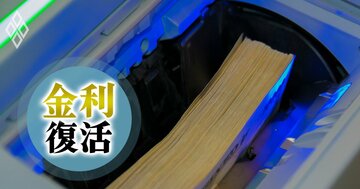Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
FRBから2年遅れの利上げ
いつものパターン踏襲の日銀?
日本銀行は早ければ3月、遅くとも4月の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する公算が大きいが、気になるのはその後どこまで金利を引き上げるかだ。
利上げによる景気の下振れや日銀の財務構造や財政の利払いへの影響も考えられるからだ。
よく言われることだが、利上げに踏み切るのは決まって、米国(連邦準備制度理事会・FRB)→欧州(欧州中央銀行・ECB)→日銀の順で、日銀の利上げはFRBから2年程度遅れるのがいつものパターンだ。
今回もマイナス金利解除が春に行われれば、2022年3月のFRBの利上げ開始からほぼ2年遅れということになる。
2年といえば、金融政策の影響が経済に表れるまでのタイムラグと大体同じ。日銀が利上げを検討するときに決まって海外経済の不確実性が高まるのは、ある意味必然と言える。
日銀の財務構造への影響も政策金利をどこまで引き上げるかによってインパクトは変わってくる。筆者の試算では、政策金利を1%引き上げると、単年度赤字になり、2.5%上げると債務超過に陥るが、いずれも政策運営能力が損なわれることはない。
ただし、「中央銀行の赤字」は深刻な本質問題を別に抱える。