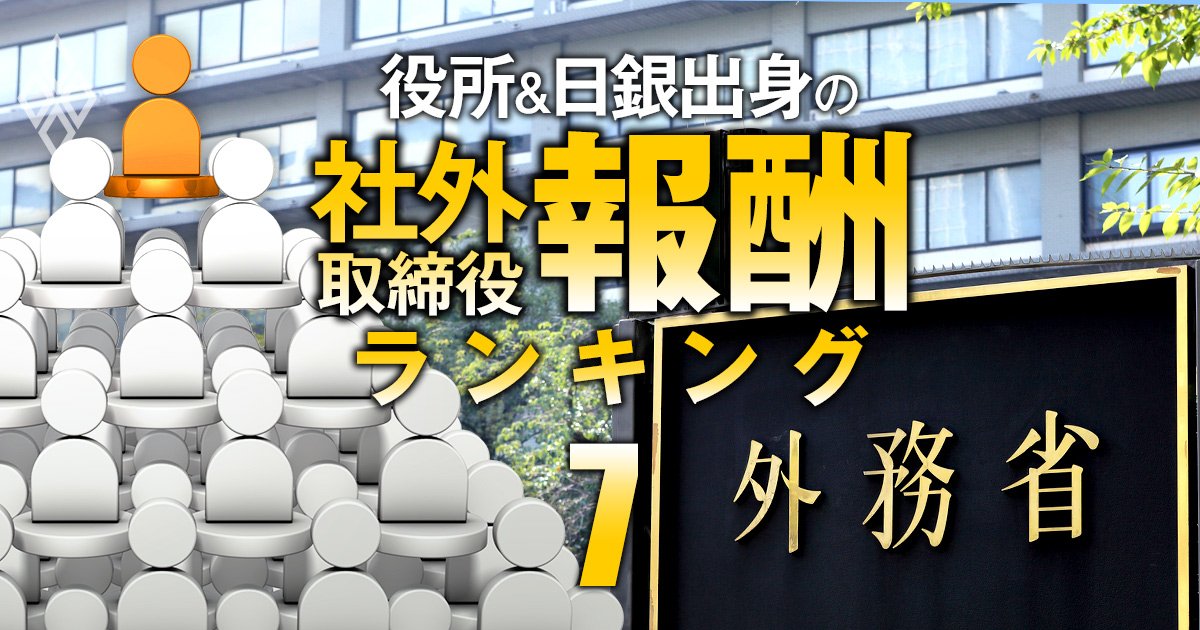植田日銀の行動は機会主義的
市場は本音を知るすべがない
何もしないことで、ひたすら僥倖(偶然に得る幸せ)の訪れを待つ――。実はこれが、日銀の戦略だった。
日銀にとっての僥倖とは何か。それは、金融政策以外の外部要因によって賃金と物価の上昇が訪れることだ。この条件が整えば、利上げができる。
植田日銀は拙速に利上げをせず、我慢し続けた。そして待ちに待った僥倖がついにやってきた。24年春闘での高い賃上げの実現だ。
日銀としてはこれで望ましい賃金と物価の流れが一歩前進したと判断した。だからもう待つ必要はないと利上げに向かった。
僥倖を待つ戦略はこれまでのところ成功したように見える。しかし、そもそも僥倖を待つ戦略とはどう理解すればよいのか。
植田日銀の戦略を理解する上では、過去の米国の事例が参考になる。89年12月のことだ。当時の連邦公開市場委員会(Federal Open Market Committee=FOMC)の議題は、高インフレ(消費者物価上昇率で約5%)の克服のために利上げをすべきか否かだった。
FOMCのある参加者が発言した。「何もせず待てばよい」と。インフレは進んでいるというのに、どういうことか。その理屈はこうだ。
利上げをすれば失業が増える。インフレの鎮静化は必要だがそのコストを誰も払いたくない。
だったら、何もせずに待てばよい。待っているうちに不況が来る。そうすれば嫌でもインフレ率は下がる。もしその不況で十分に下がらないとしてももう少し待てば次の不況が来る。そうこうしているうちにインフレ率は所望の水準まで下がるだろう。この方法であれば利上げで余分なコスト(失業)を払うことなくディスインフレ(インフレ率の引き下げ)を実現できる。
この考え方はディスインフレの機会主義的(opportunistic)アプローチと呼ばれ、注目を集めた。賢い方法のように見えるだろう。
しかし反対論者は次のように主張した。
米国の中央銀行制度である連邦準備制度(Federal Reserve System=Fed)の議長が5%は高すぎる、本音は2%まで持っていきたい、しかし失業のコストを払うのは嫌なので機会主義的に行動すると決めた、としよう。その場合の議長の行動は「何もしない」だ。
これに対して、仮に議長が本音では5%のインフレでちょうどよいと考えていたとする。この場合の議長の行動も「何もしない」だ。
この例では、どちらの議長も何もしないという点で同じだ。ということは、市場は、何もしないというFedの「行動」から議長の本音を知るすべがないということだ。
したがって、仮に議長が前者のように「5%のインフレ率は高すぎるので、2%まで持っていきたい。しかし失業のコストを払うのは嫌なので機会主義的に行動しよう」と考えて行動していたとしても、市場からは後者のように「本当は5%のインフレでちょうどよいと考えているのではないか」と勘繰られるリスクが生まれる。つまり、Fedへの信認(credibility)が揺らいでしまう。
話を日銀に戻そう。賃金と物価が上がることを祈りつつ積極的な緩和をしない、何もしないで僥倖を待つことを選択してきた植田日銀は機会主義だったとみることができる。そうだとすると日銀への信認が損なわれることはなかったのだろうか。
じっと待つだけで何もしない。そして春闘での賃上げという僥倖が来ると即座にそれに便乗して利上げをする。
このような日銀の「行動」だけを観察していた異星人(日本語も英語も理解できない生物)がいたとすれば、その異星人は「日銀は賃金と物価を上げたがっている」と推理することは決してない。むしろ賃金と物価の上昇を嫌がり、それを阻止しようとしていると推測するだろう。
どうやら異星人は東京やNYのマーケットに潜んでいるようで、日銀への信認は揺らぎつつあるように思う。
中央銀行の「行動」と言葉は、通常、同じ方向を向く。それによって言葉の重みが増す。
これに対して、今の日銀は、行動と言葉が違うという意味で、非常に特殊な状況にある。中央銀行のコミュニケーションは常に大事だが、その重要性はいつにも増して高まっている。