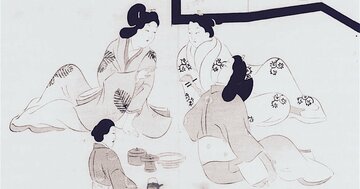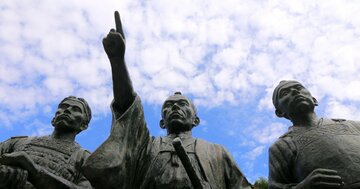写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
江戸でただひとつの幕府公認遊廓といえば吉原遊廓。当時の吉原は流行の発信地だったが、辺鄙な場所にあったため市街地に点在し「岡場所」と呼ばれる違法な遊女屋に足を運ぶ客も少なくなかった。しかし、それらの岡場所のおかげで吉原遊廓は最盛期を迎えることとなる。気鋭の研究者が、吉原の歴史を紐解く。※本稿は、高木まどか『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(新潮社、新潮新書)の一部を抜粋・編集したものです。著者の苗字は正しくは「はしごだか」。
多い時には5~6000人もの遊女が
生活していた吉原遊廓
遊廓はなぜ「遊廓」と呼ばれるのかをご存じでしょうか。それは、遊廓が堀や塀で周囲から区切られていたことに由来するといわれます。
吉原遊廓をぐるりと囲んでいたという「お歯黒溝(おはぐろどぶ)」は有名ですから、ご存知の方も多いでしょう。当初は幅五間(約9メートル)もあったというこの溝があることに加え、出入り口は基本的に「大門」ひとつ。
そうした構造であったが故に、公許の遊里は城郭(城の周囲に設けた囲い)にみたてられて「くるわ」(曲郭・曲輪)と呼ばれるようになり、ひいては「遊廓」「遊郭」とも称されるようになったといいます。こうした遊廓の構造はもともとは中国の遊里に由来したらしく、それを京の遊里が真似て、吉原をはじめとした各地の遊廓もそれに倣ったとか。
そんないわれがあるとおり、遊廓とは買売春の許された区域全体を指す言葉です。遊廓=遊女のいるお店を連想する方もいるでしょうが、個々のお店は遊女(女郎)屋・妓楼(ぎろう)、揚屋(あげや)、置屋(おきや)といった呼び方をします。
さらにいえば、遊廓は「遊里」や「色町」などとも呼ばれるように、ひとつの「町」でした。吉原の場合、四角く区切られた区域のなかにはじめ江戸町一・二丁目、京町一・二丁目、角町といった5町が設けられ、のち揚屋町、堺(境)町、伏見町が増設され、都合8町にわけられます。
このなかには、遊女屋のみならず、茶屋やその他雑貨店(酒屋・小間物屋・薬屋など)も軒を並べていました。外に出ることを禁じられた遊女はもちろん、遊女屋関係者、その他の店のひとたちがこの町に集まり住んでいたのです。
江戸期の吉原は、わずか2万坪程度。その狭い区域に、300軒前後の遊女屋がずらりと並んでいました。市中と隔絶されたこの土地では働く遊女は少なくとも3000人、多い時期には5~6000人ともいわれます。