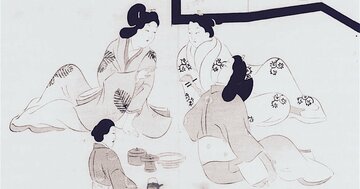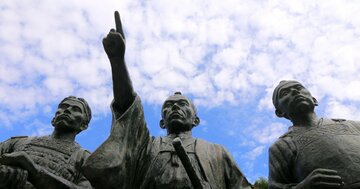こうした主張の背景に、市中で営業する違法な遊女屋を潰したいという思いがあったことはいうまでもありません。
吉原は、徳川幕府がひらかれてまもない元和3年(1617)に、その設置を許された買売春公認地区です。幕末にいたるまでは、江戸における唯一の公認遊廓でした。一方で、吉原の経営をおびやかす違法営業の遊女屋もまた、江戸市中に数多くありました。たとえば深川や本所、根津や赤坂界隈などがそうでした。このように違法な遊女屋の集まる場所を、江戸では岡場所と呼びます。
岡場所は、江戸時代をとおして、吉原にとって憎き敵、目の上のたんこぶでした。吉原は岡場所に客が流れることに腹を立て、その取り締まりをたびたび公儀へ申し出ています。何度取り締まろうとご法度の遊女屋はすぐに復活するのですが、そのいたちごっこの一端を書き留めたのが、先に挙げた史料なのです。
吉原が主張していた「遠い」という利点は、言うまでもなく、風紀上の観点から考えればです。足を運ぶ側の客にとっては、とんでもなく不便であったことは間違いありません。もちろん、吉原側も本気で市中から遠いことが良いと思っていた訳ではありません。ここで述べているのはあくまで公儀に対する建前で、本音は別のところにありました。
吉原ははじめ葺屋町(現・中央区日本橋人形町・富沢町)に設けられ、明暦3年(1657)に幕府の命令によって浅草に移転しましたから、はじめから不便な場所にあったわけではありません。
京都の島原遊廓もそうですが、遊廓は市街地の開発にともない、辺鄙な地に移される傾向にあります。遊廓が街の中心地にあっては風紀上よろしくないからです。ただ、吉原が辺鄙なところに置かれれば、違法の遊女屋が市中にはびこることになるのは必然です。まさに本末転倒。江戸の名所としてその名を轟かせながらも、吉原が執念深く岡場所のお取り潰しを願ったのには、そうした背景もありました。
違法な遊女屋の
取り締まりによる副産物
岡場所は吉原にとって目の上のたんこぶだった訳ですが、岡場所の取り締まりには副産物もありました。それは人材の獲得です。
岡場所で働く違法な私娼は隠売女と呼ばれましたが、彼女たちは取り締まりによって身柄を拘束されると、しばしば吉原で働かせられました。
とりわけ初期の吉原に大きな影響を与えたのは、寛文8年(1668)の頃におこなわれた岡場所の摘発による隠売女の流入です。