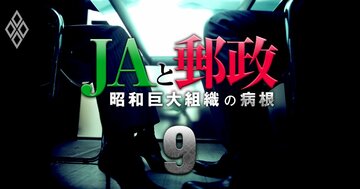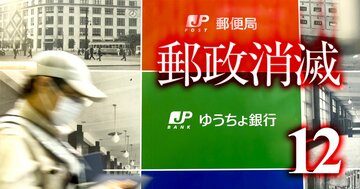写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本郵便が公表している放棄・隠匿事案は、2018年度以降だけで少なくとも30件以上。厳しい処罰が課せられる“犯罪”でありながら、なぜ郵便物や荷物の放棄・隠匿が後を絶たないのか。調べていくと、現場の苦悩を理解しない、日本郵便の的はずれな対策の実態が見えてきた――。※本稿は、宮崎拓朗『ブラック郵便局』(新潮社)の一部を抜粋・編集したものです。
放棄された郵便物が
祠の下から発見された
残業をせずに配り終えろ――。そんな無理な指導によって引き起こされている弊害の1つだと思われるのが、配達員による郵便物や荷物の「放棄・隠匿事案」だ。
日本郵便が公表している放棄・隠匿事案を集計すると、2018年度以降だけで少なくとも36件。
例えば2020年9月に発表された事案では、佐賀県の30代の配達員が、556個の荷物を配達せず、配達エリア内にある祠の下や、空き家の郵便受け、自家用車に隠していた。警察から「祠の下から荷物が発見された」という連絡が佐賀北郵便局にあり、判明している。
郵便法では郵便配達員が郵便物を隠したり、捨てたりした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されており、発覚後に日本郵便が警察に相談し、配達員が逮捕されるケースも目立つ。
多くは、捨てられた郵便物の発見者からの連絡や、「郵便が届かない」といった顧客からの相談で発覚している。ただし、企業が不特定多数の顧客に宛てたダイレクトメールなどは、届かなくても、送った側、送られた側とも気付きにくい。発覚していない事案、公表されていない事案がある可能性を考えると、公表された件数は氷山の一角かもしれない。
なぜこんなことが起きるのか。過去41件の放棄・隠匿事案について、配達員の動機を分析した内部資料によると、「配達できなかった郵便物を持ち帰って怒られたくなかった」「配達が遅いと言われたくなかった」が合わせて8割を占めている。
「私のような犯罪者に
なってほしくはありません」
本来、こうした問題が起きれば、個々の配達員の負担を軽減したり、配りきれない際に周囲に相談できる仕組みを作ったりする対応が求められるだろう。しかし、日本郵便の対策は必ずしもそうではない。
管内で放棄・隠匿事案が発生した日本郵便東海支社では、2019年7月、各郵便局長に対し「郵便物等の放棄・隠匿犯罪根絶に向けた取組強化」を指示する文書を出している。
この文書では、取組強化策の1つとして、役職者が毎月1回、朝礼の場で、配達業務に携わる全ての局員を集め、「犯罪者の手記」と題された文章を読み上げるよう求めていた。
関係者から入手した「手記」には、郵便物を隠した配達員たちの「告白」がつづられている。
「私は逮捕されました。その後は、近所から白い目で見られているような引け目を感じる毎日で、逮捕の事実が新聞に実名入りで掲載されたこともあり、小学校に通う2人の子どももいじめられたようでした。これらはすべて、私の犯罪によるものなのです」
「懲戒解雇を言い渡され、仕事を失った瞬間、私は、ようやく事の重大さに気がつきました。これまでの学歴・職歴、すべてが意味のないものになってしまった瞬間でもありました。なんて事をしたんだろう。自業自得だ。ウワー!」