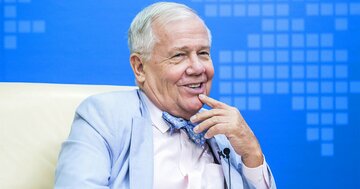「年金制度はもう崩壊している」
それでも徴収する政府の“常套手段”
退職金や厚生年金は自分や企業が積み立てたお金に加え、運用のリターンも含まれた上で計算されている。このあたりはざっと説明するが、その計算で用いられているのが「割引率」であり、この割引率は国債の利回りにほぼ連動している。
勘のいい読者であれば、もう気づいたであろう。そう、国債の利回りが長年にわたり低かった日本では、運用リターンがほぼ期待できず、その不足分を企業もしくは本人が負担することになる。
最悪の場合、負担ができない企業は退職金制度が破綻するような事態が生じるのである。
もう1つ、先ほど年金も同様の仕組みで運用されていると紹介したが、正確には違う。日本の年金制度はすでに崩壊していると言えるからだ。というのも、現在年金をもらっているシニア世代の原資は、自分たちが納めたり、金融商品の運用リターンで得たりしたものではなく、今まさに年金を納めている、生産世代が納付したお金を利用しているからだ。
このような年金制度は「賦課方式」と呼ばれるが、ここでもインフレ率の嘘などと近しい、政府の常套手段が窺える。日本をここまで育ててくれたシニア世代を助けましょうと、国民の公助の心に訴えかけることで、年金を徴収しているからだ。
「投資で資産が増える」
理解と環境の整備が必須
確かに、日本の年金制度は当初から賦課方式であったから、バブル経済も含め、好調な景気が長きにわたり継続すれば、問題はなかったのかもしれない。しかし、バブルは弾け、対応策もうまくいかず、日本は失われた30年を歩むことになる。
つまりこの30年間、年金や退職金は大きなリターンを得ていなかったのである。そのため現に、企業においては年金制度の廃止や減額といった、痛みを伴う行動に出ているところもある。
一方で、国は動いていない。むしろ逆で、年金を支払っている人に対して、より多くの年金を払ってもらえないか、といったアピールに出ている。このような痛みを伴わない、小手先の政策で改善するはずがかない。
ここからの2つは、悪影響を受けながらも、改善の兆しが見られるテーマについて触れたい。まずは、若い世代の貯蓄意欲の低下である。
日銀の金融緩和政策は日本人、特に若い世代の貯蓄の意欲を減退させ、実際に貯蓄率を停滞させてしまった。銀行に預けていてもほとんど利子がつかないのだから、預けようと思う人がいないのは、当然と言えるだろう。
このような状況から抜け出すには、まず投資によって資産が増えることを多くの人が理解し、その方法を見つけ、実施できる環境が整っていることが必要だ。