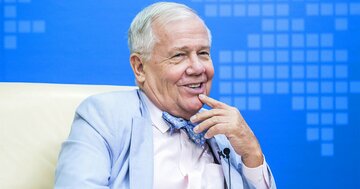幸いなことに日本市場は35年間の低迷を経て、ようやく投資が増え始めている。
NISAや新NISAなど、投資意欲を呼び込む環境が、整いつつあるからだ。政府がようやく動いた、とも言えるだろう。現在の状況が続けば、状況は改善するかもしれない。
日本の消費者は
なぜ物を買わなくなったのか?
続いては、消費者の支出意欲の低下である。まずは、消費マインドと個人消費について、そしてこれらが日本経済とどのように結びついているか、考えてみたい。
一般的に物価が下がると予想される場合、消費者は購買を控える傾向がある。このような行動傾向は、インフレで物価が上昇する状況下に見られる、積極的な消費行動とは表裏一体だ。
それでは日銀がインフレを起こせなかったことが、消費者の消費意欲を減退させる要因となったのだろうか。この点について、日銀の金融政策が経済に与えた影響を含めて考察してみたい。
消費者の行動を理解する上で重要なのは、実際の支出だけでなく、消費者の自信や心理的な側面も考慮に入れることだ。現在の日本の消費者の心理面は楽観的とは言い難く、自信に満ちているとも言えない状況にある。
このような日本人の現在の心理状況は、日常生活のさまざまな場面に表れる。以前ほど気軽に外食をすることが減り、銀座の高級店で銀のゴブレット(器)を購入するような贅沢な消費行動も、減少している。
消費行動の変化は単に経済的な要因だけでなく、社会全体の雰囲気や将来への不安とも密接に関連している。日銀ならびに政府が取り組んできた長年にわたる金融緩和政策は、こうした消費者心理にも大きな影響を与えてきたと考えられる。
長期的なデフレから
ようやく抜け出そうとしている
具体的には、長期的なデフレであり、政府や日銀は2%と明確なインフレ率の達成目標を掲げており、対策を行っているにもかかわらず、一向に達成できなかったことだ。このような長年にわたる日銀の金融政策の失敗が、将来に対する消費者の見通しを不安にさせたのだ。