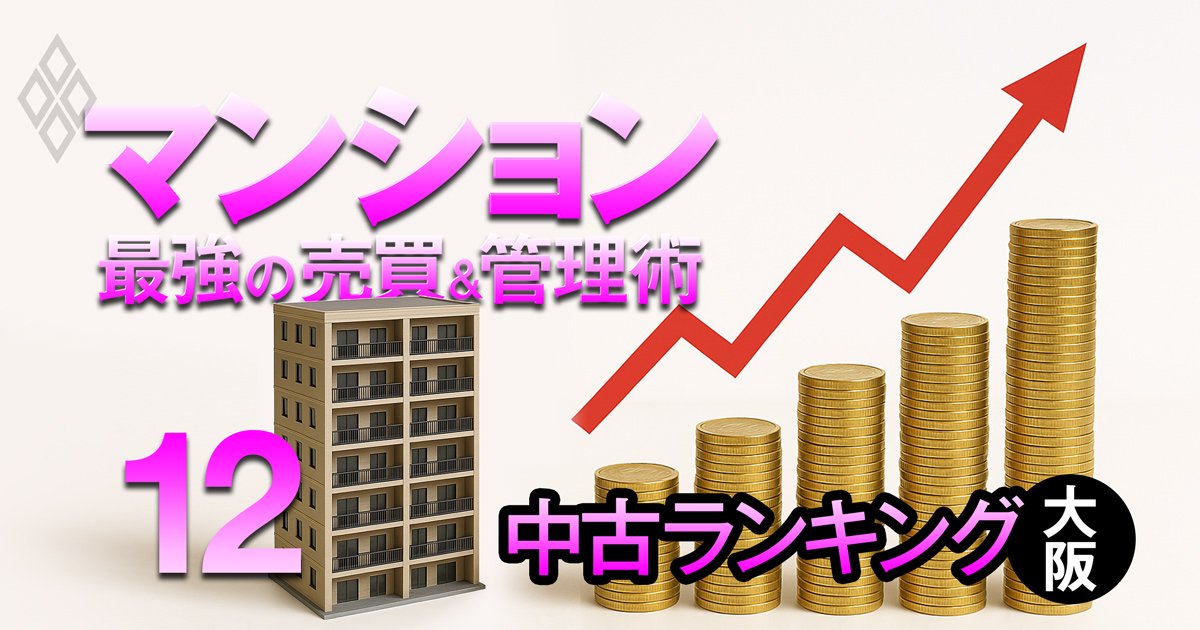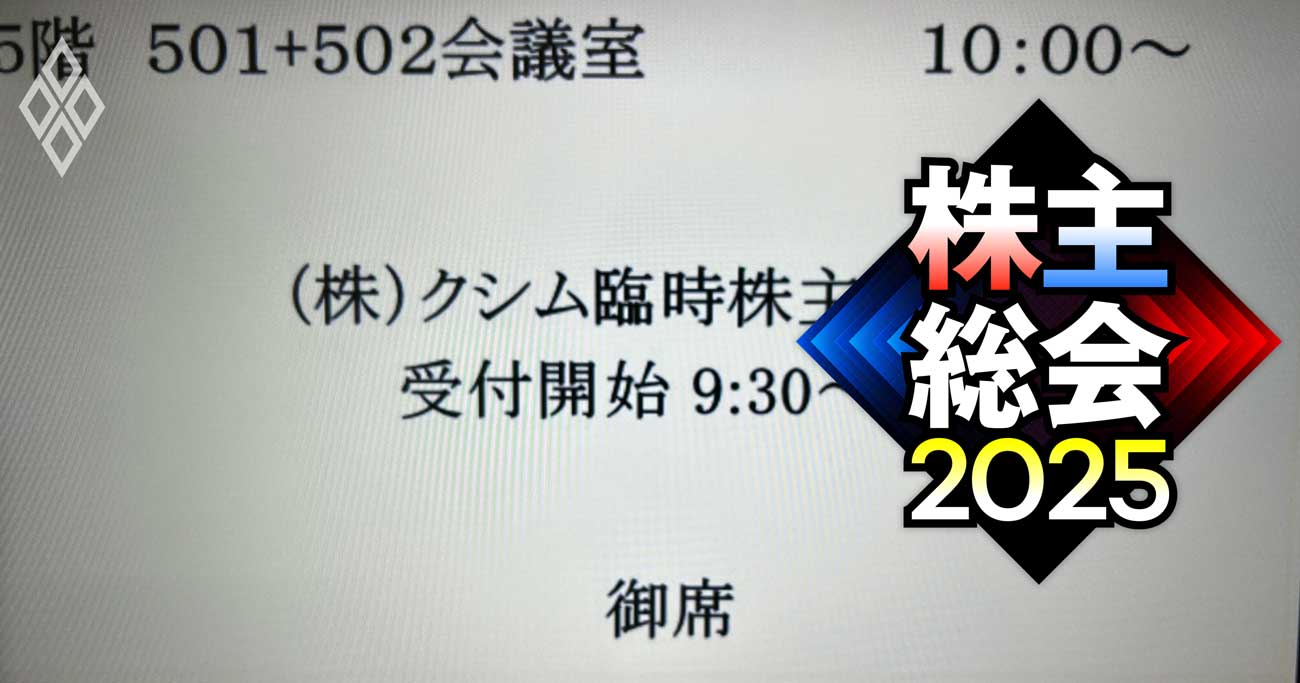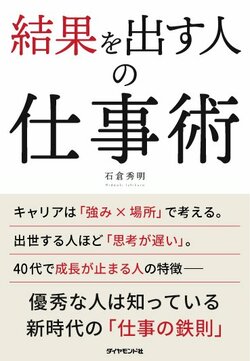 石倉秀明著『結果を出す人の仕事術』
石倉秀明著『結果を出す人の仕事術』
「なぜそこまでして男女一緒にしなければいけないのだ」と言う人もいる状態である。正直、ジェンダー平等の問題はさまざまな意見があるだろう。しかし、少なくとも筆者が一緒にプロジェクトを行っている会社は、「2030年代に女性管理職をXX%まで上げる」という目標を掲げ、さらに男女の賃金格差をなくすことにコミットしている会社だ。そういう会社の人事部門の役職者、役員がこのような発言をしていると考えると、非常に驚く。
しかし、最大の問題はそこではない。統計分析の結果、出た「事実」があるにもかかわらず、それよりも自らの感情や感覚、経験値を優先してしまっている点である。
「不都合な事実」に直面したとき
リーダーとしての適性が見える
もちろんデータや分析は万能ではない。統計分析はあくまで「結果」であり、原因ではないので、過去の意思決定や施策の失敗などを議論するものではない。データとして取得していない項目や変数についてはその影響を明らかにすることはできない(例えば、上司のもたらす影響を調べようと思っても、歴代の上司の属性や評価などをデータとして残していなければわからない)。
だが、何らかの要因が積み重なった現実として、統計分析の結果が出ていることは事実だ。今回のケースで言うと、「男女で賃金の差がある」「説明できない要因が男女賃金格差の約3~4割を占めている」、また「労働時間の長さ」「長時間労働を行う人がバイアスにより高く評価されること」などは紛れもなく、「事実」である。
こういった残酷な事実やデータが出た場合の態度で、その人がどのように現実を捉えるかがわかる。大きく分けると、2つのタイプが存在する。
1つ目は、事実を自分の都合の良いように解釈したり、何かしらデータや分析結果が現実と齟齬があることを根拠なく指摘しようとしたりするタイプだ。また、この結果は誰が悪いのか、何が良くなかったのかと犯人探しをすぐに始める人もいる。言うならば、「誰かのせい思考」である。
もちろん、統計手法に誤りがある可能性もあるので、分析に対する建設的な批判が全て悪いわけではない。しかし、ビジネスの場で求められているのは、そのような態度ではないだろう。