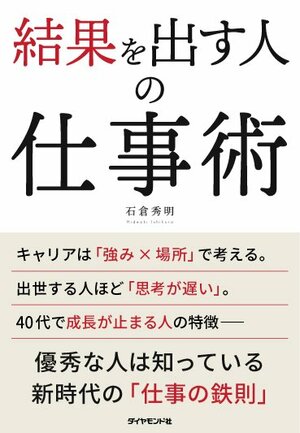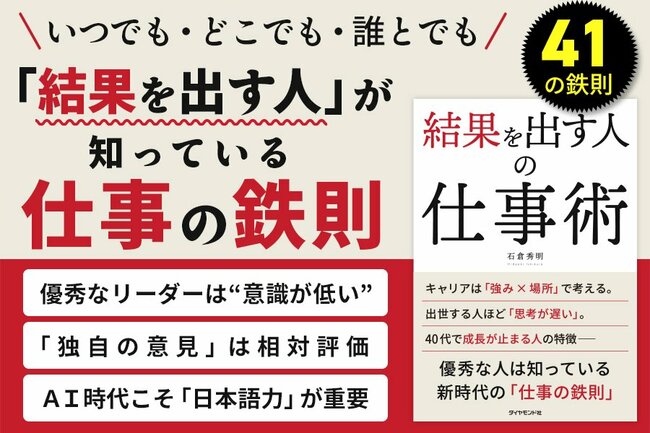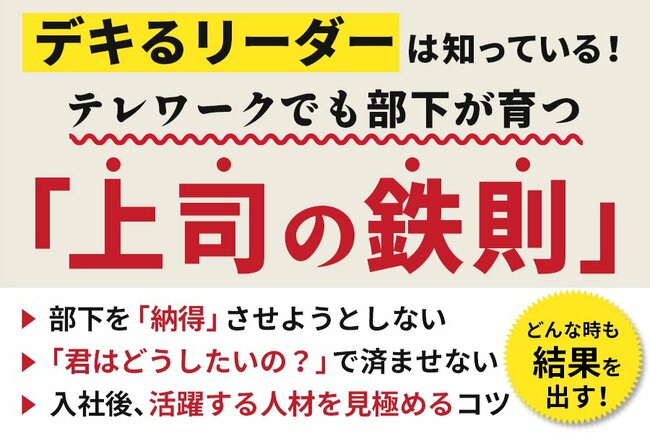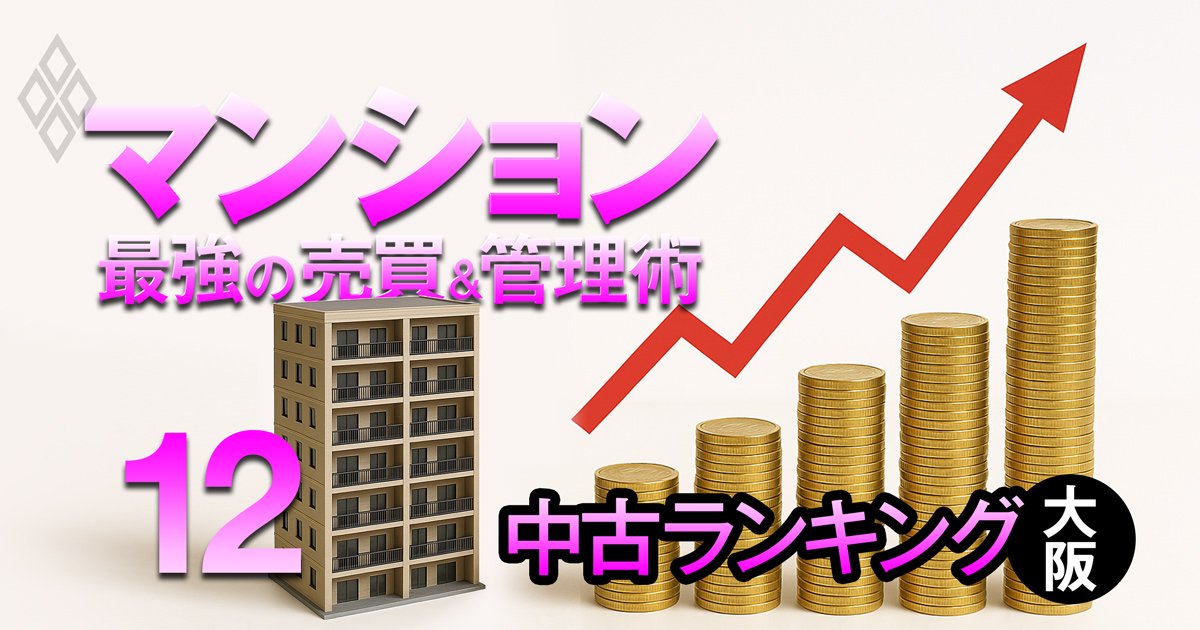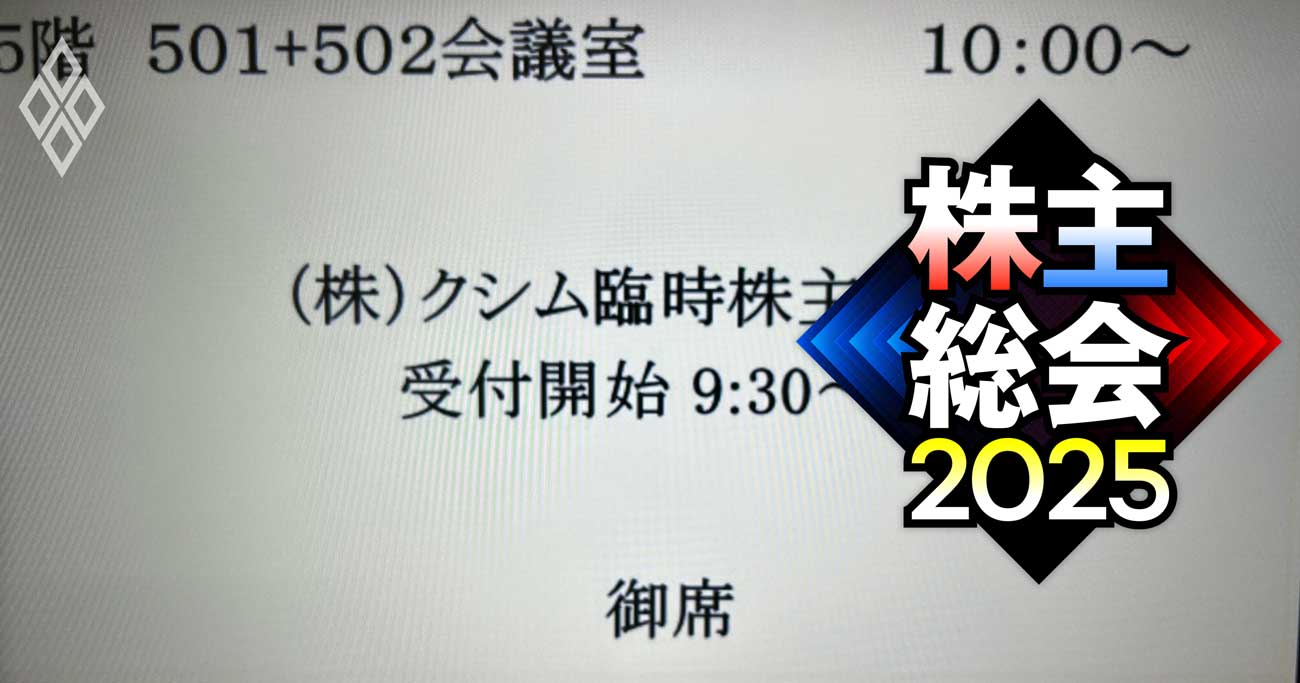2つ目が、事実をそのまま受け止め、「ではどうするか?を考える」「本当の要因を知ろう」とするタイプだ。このタイプは、どんなに自分にとって都合が悪いデータや事実が出てきたとしても、それをそのまま受け止め、改善することに目を向ける。
つまり、どこまでも「問題解決思考」なのだ。むしろ問題を明らかにでき、解決する糸口が見つかるからこそ彼らはデータや事実を重視するし、その結果出てきた問題をどう解決するかにしか興味がない。
役職が上がれば上がるほど
「痛みを伴う課題」を避けて通れない
これら2つのタイプ、どちらに会社の重大な部署を任せたいかは明白だろう。
筆者は上場企業の取締役を務めていた時、会社の重要な役職であればあるほど、後者の人材であることを重視した。そうでなければ登用しなかった。
管理職、特に役員に近づけば近づくほど、主な仕事は問題の発見とその解決になる。しかも現場ではなかなか改善できないこと、解決できないことに対して大胆な意思決定をして問題を解決することが求められる。
そのようなポジションに前者のタイプは登用できない。問題を解決してくれないどころか、問題発見のヒントになるデータや事実が出てきているにもかかわらず、それを見過ごしてしまったり、報告してくれなかったりする可能性が高いからだ。
失敗を認めない、自分が責任を負うかもしれないなど、「自分の保身」ばかりを考えているタイプを管理職に据える、特に役員に近いポジションに置くことは会社にとってリスクが大きい。
役職が上がれば上がるほど、部下では解決できなかった事案、部下では判断できなかった事案を扱わなければならない。そのほとんどは、どちらかというとネガティブな事案や誰かにとって痛みを伴う事案である。そうでなければ自分のところに上がってくる前に解決しているからだ。
つまり、会社で役職が上がるということは、どんどん不都合な事実、課題にばかり向き合うことになる。だからこそ不都合な事実やデータをむしろ歓迎し、それをきっかけとして問題解決の糸口にできる人こそが、より役員に近づいていくのだと思う。