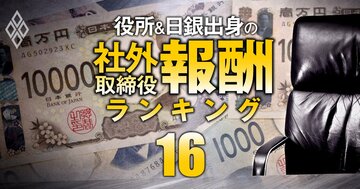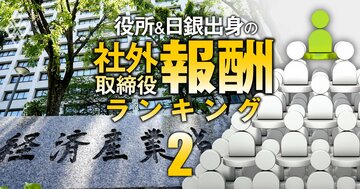初代局長を務めた内閣人事局の成果の一つは
中央省庁が人材マネジメントを意識したこと
近年、若い職員の給与は上がってきていますが、中堅クラスの処遇が、その方々と同世代で(企業など)外で働いている人たちと比べてどうなのか、という感じがします。
仕事を給与だけで選ぶわけではありません。やりがいとか、自己実現ができるかとか、あるいは自分を磨けるのかってことも大きいと思います。けれども、それなりに処遇が付いてこないと、なかなか(人材レベルの維持は)簡単ではありません。処遇面をしっかり改善するのと、納得できる評価の仕組みが大事です。働きを評価してもらうことが次のやりがいにつながります。
――財務省が公務員の人件費の増大を許容する姿勢を見せないと、人事院が思い切った賃上げの勧告に踏み切れないとみられています。そういう訳で(加藤財相の発言が)注目されています。
予算的なことは当然ある。それから、世の中からどう見られるかということもあります。最後は、期待される人材にどういう形で働き続けてもらうのかということに尽きます。そういったところも含め、まず人事院でいろいろ議論されると思います。
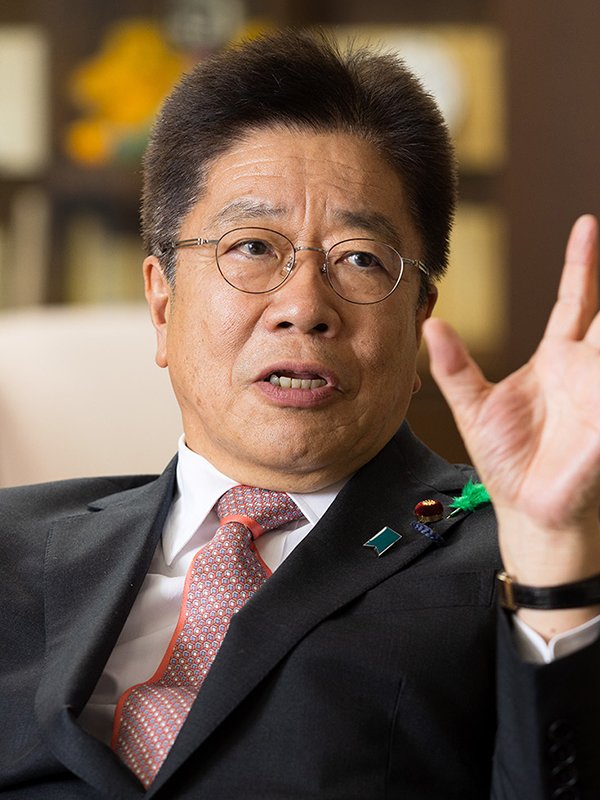 かとう・かつのぶ/1955年生まれ。東京都出身。東京大学経済学部卒業。1979年年大蔵省入省。衆院議員秘書を経て、2003年衆議院議員初当選。14年内閣人事局長、15年一億総活躍担当相、女性活躍担当相、17年厚生労働相、18年自民党総務会長、19年厚労相再就任、20年内閣官房長官、24年から現職。 Photo by Y.N.
かとう・かつのぶ/1955年生まれ。東京都出身。東京大学経済学部卒業。1979年年大蔵省入省。衆院議員秘書を経て、2003年衆議院議員初当選。14年内閣人事局長、15年一億総活躍担当相、女性活躍担当相、17年厚生労働相、18年自民党総務会長、19年厚労相再就任、20年内閣官房長官、24年から現職。 Photo by Y.N.
――公務員の人材を維持するには、政治家からのパワハラや、組織内のパワハラを是正する必要があります。地方公務員も同様で、兵庫県では知事のパワハラが問題になりました。
働きやすい環境づくりは大事です。ハラスメントを受けることで、その人の力が出し切れないとなると、本人にとっても組織にとってもプラスではありません。
組織内のハラスメント対策だけでなく、カスタマーハラスメントといった組織外への対処も含めて、働きやすい環境をつくっていくのはトップマネジメントの大事な役割の一つです。
――役所は人材マネジメントで、企業より遅れています。
私は内閣人事局長だったときから、マネジメントはおのずとできるものではないから研修をしっかりやるべきだと言ってきました。実際、財務省でもマネジメント教育をやっています。
野球でも、優秀なプレーヤーが良いマネジメントをするとは限らない。プレーヤーとしての力とマネジャーとしての力は、多分同じではないのです。
――公務の現場は限界にきていませんか。地方も含めた、道路の管理や教育といった現場に近い職場、首相をサポートする面々や対米交渉のチームといった国家の中枢、それぞれのレイヤーでの公務員の能力をどう評価していますか。今の機能を10年後も維持できるでしょうか。
前者のレイヤーでいえば、教育現場の課題はかなり指摘されています。教師の処遇も含めてさまざまな問題があり、残念ながら心を病んでしまう方もいらっしゃる。現状は、持続可能ではないともいわれています。
一方、中央官庁では、より政策的な仕事が多くなる。最終的な判断は大臣や政治家がしますが、そこに至るまでのプロセスで、現状分析とか、どういう選択肢があるのかといった部分は、(官僚が)どこまで(判断材料を)つくってくれるのかが重要で、その点で、中央省庁で働く方々への期待は大きいのです。
――有望な人材が民間に流出して、政策立案能力の低下が懸念されています。どうやって欠員をカバーしていきますか。
一つは、やはり魅力ある職場にすること。もう一つはリボルビングドア(回転扉。現役のビジネスパーソン、官僚が、勤務先として企業と省庁を行きつ戻りつすること)のような形で、一度外の空気を吸って違う視点を身に付け、戻ってきてもらうことです。民間では社員の半分ぐらいが中途採用になってきている。多様なキャリアの人が活躍できるのは、良いことではないでしょうか。
――(政治家が、有能な人材を省庁の幹部として登用する)政治任用が局長級などで増えていくのでしょうか。
政治任用というと、日本の役所と米国の政治任用とではちょっとニュアンスが違います。
公務員改革の中で、内閣人事局が介在して、審議官以上ぐらいのポストの人たちは、その集団に入れるかどうかをチェックされ、その上で、局長に就くことになっています。大臣や官邸が、(幹部人材に望ましいかどうかを)見る仕組みはすでにあるわけです。
――リボルビングドアが当たり前になり、多様な人材が活躍できるチームをつくるために、クリアすべき課題はありますか。
現在は、省庁ごとの仕事の流儀みたいなものがある。それはそれでいい面もありますが、別の組織から来た人がぱっと適応して働けるように、なるべくユニバーサルなものにしていくのが大事です。
民間でもいわれていますが、着任したらまず秘書を呼んで、「このパソコンどうやって動かすの?」と聞かなければいけないようではすごく時間がかかります。
――財務省はかつて公務員志望の学生から一番人気でしたが、最近はどうでしょうか。人材の獲得と離職防止のために何が必要ですか。
財務省だけではなく、昔に比べると厳しくなってきたと採用の担当者から聞いています。ただ、(志願者の母数となる)学生らの数がかなり少なくなっています。それから学生の選択肢も相当広がってきて、商社や銀行などに加え、コンサルなども出てきてるし、スタートアップを立ち上げる人も増えています。
そういう中で、公務員の仕事の面白さとか、やりがいをしっかり発信していくべきです。
――「財務省解体デモ」が行われているのは、採用にとってネガティブだと思います。職員に対してどういった話をしていますか。