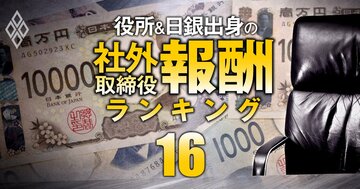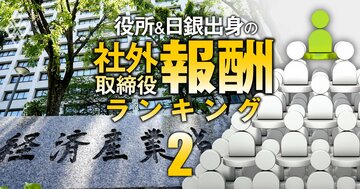財務省解体デモの背景に「国民の困窮」
問題に対応する知恵を出し、役割をアピールする
デモの背景にどういう国民の思いがあるのか。やっぱり物価上昇とか、生活の厳しさがあると思う。政治として、そういった思いにどう対応するのか、そのための知恵を役所からどう出していくかです。
(財務省を志望して)来る人から見ると、確かにネガティブな部分はあるとは思いますが、そこのところをわれわれ自身がどう乗り越えていくのか(が重要)です。財務省なら財務省の、中央官庁なら中央官庁の仕事がどういうもので、どんな役割を果たしているのか、そして国民の皆さんの生活にどうつながってるのかをしっかりPRしていくということがすごく大事です。
今はインターネットやSNSがあるから、ああいうデモにもつながってるのかもしれないけれども、逆に言えば、ネット社会になった中で、SNSなどを使いながら、いかにタイムリーに発信していくのか勉強しなければいけないと思います。役所の広報は堅いですから。
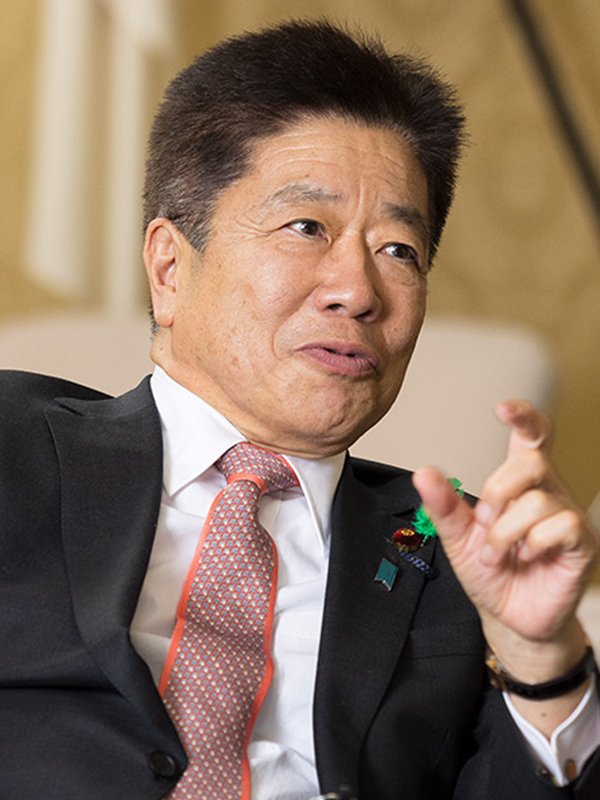 Photo by Y.N.
Photo by Y.N.
――最後に非正規公務員の問題についてうかがいます。非正規の教師と正規の教師がいて、給与が倍ぐらい違うのに両方ともクラスの担任を持っているという実態があります。欧米の公務員ならば「待遇格差があるなら一定以上は働かない」と拒否しますが、日本人は強く主張しない傾向がある。我慢して働くし、現場力も高いからオペレーションは破綻しない。しかし、現場の努力でカバーするのは同一労働同一賃金の原則にも反するし、ゆがみをこれ以上放置すれば、国民生活に影響が出るのではないでしょうか。
(非正規公務員には)幾つかパターンがあります。希望の時間帯だけ働きたいから非正規として働く人がいる一方で、本来は正規で働きたいけれど、というケースもある。特に教職員の方で、試験は受かったんだけど(正規では)採用されず、もう少し(非正規で)頑張れば、将来は、みたいな話もあります。
いろんなケースがあるので一概には言えませんが、基本は、正規でやるべき仕事は正規が担うべきだし、非正規にするならば、同一労働同一賃金は当たり前のことです。
非正規と正規では、職業能力の研修、人材開発において(力の入れ方に)違いがあります。そういったことも踏まえ、正規としての活躍を期待する人たちには正規化に向けてのいろんな支援をする、そういう努力は必要です。
地方公務員もそうですが、以前は(非正規の方は)ボーナスがなかったのですが、それが出るようにしてきました。私は厚生労働相として、正規と非正規の人で同じように働いているならば一方だけボーナスが出ないのはおかしいと言ってきました。金額の多寡はあるかもしれませんが、全く出ないのはおかしいんじゃないか。そこはしっかりやってくださいと求めてきました。
――民間は給与が上がって、官民の給与格差は広がっています。
新型コロナウイルスの感染拡大やデフレの中で、皆が我慢してきました。賃金が上がり、物価が上がるようにしましょうとやってきて、モメンタムが変わろうとしています。民間が先に動くけれども、それに合わせて公務員、あるいは公的な制度で運営されている医療とか教育、保育も含めて改善していかないと社会全体として賃金が上がっていきません。
――加藤財相がそういった前向きなメッセージを発すると、公務員に希望が出てくると思います。
そういう(賃上げ基調の)中で、より高いパフォーマンスを出していく。公務で国民の皆さんの期待に応えることが一番大事なことです。そのことがまた働く人のやりがいにつながるという、良いサイクルをつくっていくのがわれわれの仕事です。
Key Visual:SHIKI DESIGN OFFICE