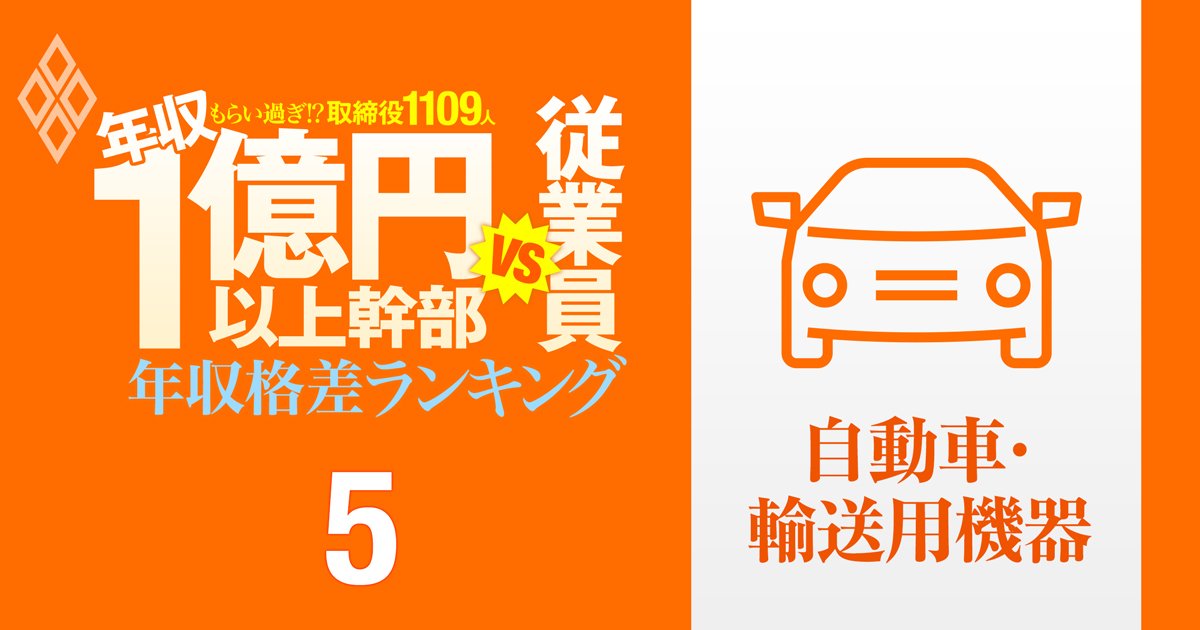標準化された学習
不安があれば外部リソースを活用
2.標準化
もう一つの特徴は「標準化」です。公立学校では、個性的な教育よりも、ある程度均質な教育が提供される傾向にあります。これは良い意味でも悪い意味でも「平均化」されるということです。特定の先生の色が学校全体に出にくく、教育内容も文部科学省の指針に沿った標準的なものになります。
標準化によって、極端に良い面も悪い面も薄まる傾向があります。例えば、体罰などの悪しき伝統が長く続くことは少なく、逆に画期的な教育改革が広がりにくいという面もあります。運動部を例にすると、強豪校の顧問が7〜8年で違う学校に異動すれば、その指導方針も変わり、場合によっては運動部の実力も変化するでしょう。
学習面の標準化も気にしておきたいところです。公立では私立に比べて「取り出し授業」など個別最適化された学習が提供されにくい面があります。これは日本の公教育が「平等教育」を重視する傾向にあるためです。特に英語教育では、私立の方が少人数制や習熟度別クラスなどを取り入れやすい環境にあります。
しかし、こうした学習面の不安は、塾や英会話スクールなどの外部リソースを活用することで補うことができます。
重要なのは、「学校任せにしない」という意識です。これは実は私立中学校でも同じことですが、子どもの教育は学校だけでなく、家庭と子ども自身の三位一体で進めていくものです。特に公立中学校の場合は、必要に応じて塾や習い事などの「オプション」を活用し、子どもの学習環境をコントロールしていく姿勢が大切です。
3.選べないこと
また、公立中学は学区によって通う学校が決まるため、選択の余地が少ないという特徴もあります。この「選べない」という点は、メリットにもデメリットにもなり得ます。選べないからこそ、地域の多様な子どもたちと交流できる一方で、特定の教育方針を求める場合には制約となります。
公立中学校を評価する際には、「公立だから劣っている」「私立が優れている」という先入観を持たずに見ることが大切です。
公立と私立の選択は、その学校の特性とお子さんの個性、家庭の教育方針との相性によって判断すべきものです。どちらが絶対的に優れているということではなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、お子さんにとって最適な環境を選ぶことが重要なのです。