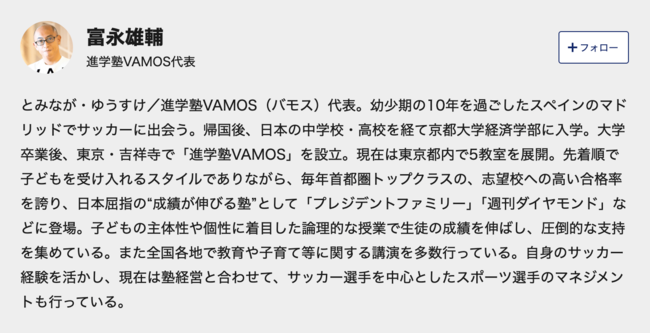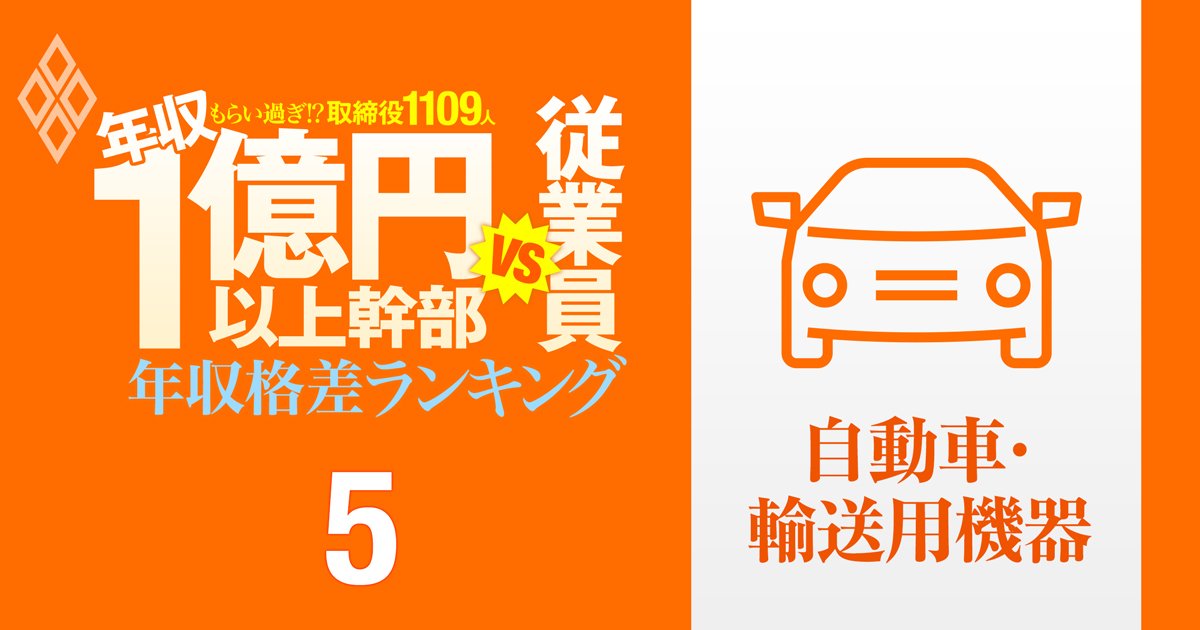トイレの状態や冷暖房設備
日常で使う場所のチェックは必須
4.通学環境
「通学環境」も考慮したいところです。公立中学校は小学校よりも数が少なく、通学距離が長くなる傾向があります。例えば東京都内では、公立小学校が約1279校あるのに対し、中学校は約613校と半分程度しかありません。
これは、家から離れていて、通学時間が長くなる可能性を示しています。通学路の安全性や通学時間が子どもの生活にどう影響するかを事前に確認しておきましょう。もし受験を考えている私立中学校が近距離にあるなら、通学のしやすさは大きなメリットになり得ます。
5.施設・設備
公立中学校の施設は自治体の財政状況や校舎の築年数によって大きく異なります。新設校や、近年建て替えられた学校もあれば、施設の老朽化が進んでいる学校もあります。
特に注目すべきはトイレの状態や冷暖房設備、ICT環境など、日常的に使用する設備です。例えば、全てのトイレが和式のままの学校と、ウォシュレット付きの洋式トイレが整備されている学校では、子どもの学校生活の快適さが大きく変わってきます。
6.情報発信
公立中学校は私立に比べて「情報発信が少ない」傾向があります。これは公立校が「選ばれる」という意識を持つ必要がないためです。学区によって通う学校が決まっている以上、学校側としては「選ばれるために情報を発信する」という動機付けが弱いのです。
そのため、学校の様子を知るためには、積極的に学校見学や説明会に参加したり、実際に登下校時間に学校周辺を訪れたりするなど、自ら情報を集める姿勢が必要です。理想としては、近所の地の利を活かして1週間ほど毎日登下校の時間に学校の様子を観察するくらいの熱意があると良いでしょう。
*****
最後に強調しておきたいのは、繰り返しになりますが「公立だから劣っている」という先入観を持たないことです。公立中学校にも熱心な教員は多数おり、学習環境も地域によっては非常に充実しています。公立か私立かという二元論ではなく、お子さんの個性や家庭の教育方針に照らして、「この子にとって最適な環境はどこか」という視点で選択することが大切です。