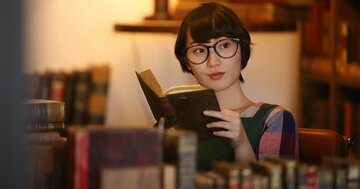もし受け取ってくれたとしても、明日も明後日も同じ野菜が余ることになります。かといって、せっかく育てた野菜を捨てるのはもったいない。誰か欲しい人はいないものだろうか。そう考えたとき、畑の脇に棚を作り、そこに余った野菜を並べて「持って帰ってください」と置いておくことを思いつく人がいたのかもしれません。いわば「無料配布所」ですね(2)。
畑の横の道を歩く人が棚を見つけて、欲しい野菜があると助かりますね。畑にご主人がいる場合は、ひと声かけて野菜を持ち帰ることでしょう。まさに面識的なやりとりです。ご主人の姿が見えない場合、お礼のメモなどを置いておくかもしれません。
お返しとして自分がおすそ分けしたいものを棚に置いて帰るかもしれません。集落を歩いていてご主人を見かけた場合はお礼を伝えることもできます。誰がどの畑の持ち主なのかがわかるからこそ、お礼を伝えることができるわけです。
信頼で成り立っていた
無人販売所が変わっていく
そのうち、誰かが「お金を取ってくれよ、そのほうが気が楽だ」と言い始めるかもしれません。お礼の品を考えたり、メモを書き残したりするのは手間です。野菜の代金を取ってくれれば、こちらも気兼ねなく野菜を持ち帰ることができる。
そんな言葉に後押しされて、畑の主人は棚の脇にザルとか箱を置き、「野菜、すべて100円」などと張り紙をするのです。ここでようやく「無人販売所」が誕生します(3)。
そうなると、人々はザルや箱に小銭を入れますが、小銭には名前が書いてありません。ご主人は誰が野菜を買ってくれたのかがわからなくなります。「いつも美味しい野菜をありがとうねー」と言われて初めて「ああ、この人も野菜を買ってくれているんだ」と気づくことになったりします。面識関係ではあるものの、誰が買ったのかがわからない関係になってしまうのです。