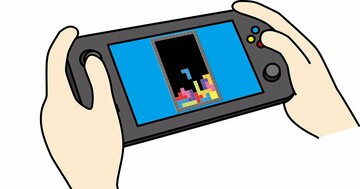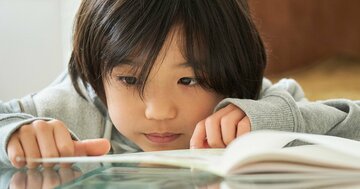心理学者ベンジャミン・ブルームは、その有名な論文の中で、1対1の個別指導が生徒にもたらす大きな利益について議論し、個別指導を受けると、受けない場合よりも生徒の学力は平均より2標準偏差上昇すると主張した。
また彼は、個別指導によってそのような学力の向上が起きることがわかっている以上、生徒の学習能力の欠如や学習する科目の本質的な性質を言い訳にするべきではないとも主張した。
しかし、個別指導は費用もかかる。生徒1人につき教師1人を雇えるような余裕のある学校はほとんどない。
「完全習得学習」という手法なら
各生徒のレベルに合わせられる
そのため彼の主張は、1対1によるサポートの利点に近づきつつも、数十人の子供たちがいる教室で実行可能な教授法を見つけることへの呼びかけとなった。
ブルームは「完全習得学習(マスタリー・ラーニング)」という手法で、その解決法を見つけたと信じていた。
完全習得学習は、カリキュラムを「教授・練習・フィードバック」のサイクルに分解する。まずは生徒に特定のセクションを教え、次にテストを行う。
しかし一般的な教室で行われるテストとは異なり、このテストは成績をつけるためのものではない。テストの出来が悪くても、生徒が罰せられることはない。その代わり、テストは純粋に、どの生徒が教材をマスターしたか、あるいはしていないかを評価するために使用される。
教材をマスターしていない生徒には、次のセクションに進む前にテストに合格できるよう、新たな説明と練習の機会が与えられる。一発で合格した生徒には、代わりに発展的な課題が与えられる。
完全習得学習は、教室での学習について、私たちが当然だと思っている慣習の多くを覆すものだ。例えば多くのカリキュラムにおいては、「初期のテストの点数が最終的な成績に反映される」という慣習があるが、これは最初に苦戦してしまった生徒に悪影響を及ぼす。
初期につまずくと、その生徒は授業で成功する可能性がどんどん減っていくのを感じてしまうのである。
これとは対照的に、完全習得学習におけるテストは成績をつけるためではなく、早い段階でつまずいている生徒を特定し、サポートするためにある。苦戦している生徒に素早く介入することで、教室環境においても1対1の個別指導の魔法を再現できるのである。