バスで上田駅前に戻った後、上田電鉄別所線で別所温泉駅に向かった。別所線は2019年10月の東日本台風で千曲川橋梁が崩落し、存続の危機に見舞われたが、国と上田市の支援で橋梁を再建し、2021年3月に全線で運転を再開した。その後の様子が気になっていたのである。
 別所温泉駅(筆者撮影)
別所温泉駅(筆者撮影)
上田電鉄親会社の社紋が
東急に似ているワケ
上田電鉄は五島慶太との縁も深い。彼は1920年、38歳で実業家に転身するまで、鉄道行政を管轄する鉄道院の総務課長(私鉄監督部門)を務めていたが、別所線と青木線の軌道特許申請は役人人生最晩年の1919年のこと。五島慶太未来創造館の展示によれば「故郷の住民の願いを実現するため、東京から技師を派遣して線路設置計画策定に協力するなどの後押し」したという。
五島は人生の最晩年、再び上田電鉄に手を差し伸べた。当時、沿線外の観光開発に力を入れていた東急は、伊豆半島で「伊豆急行」を構想、北海道の「定山渓鉄道(1969年廃止、現在は東急グループのバス事業者「じょうてつ」として営業)」を買収、そして信越エリアの拠点とすべく上田電鉄(当時の名称は上田丸子電鉄)を傘下に収めた。上田電鉄の親会社である上田交通の社紋が東急仕様なのはそのためだ。
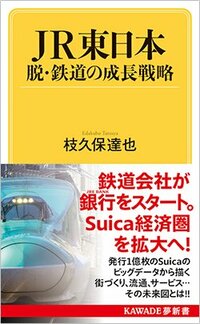 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
現在使われている車両は東急東横線などで使われていた「1000系」だ。ワンマン運転の2両に短縮されているが、赤いラインは当時の姿のまま(ラッピング仕様の車両もある)。車内も東急グループの名に恥じない水準で保たれていた。
沿線には長野大学の最寄り駅である「大学前駅」があり、筆者が乗車した平日午後3時頃も20人以上の乗車があった。観光輸送、通学輸送を中心に地域輸送を支えるが、コロナ禍の影響は小さくない。このような地方私鉄の維持に何が必要か。改めて考えさせられる乗車体験だった。
次は「どこかにビューーン!」でなくとも、候補にあった長岡や盛岡を訪れてみたい。また、別の候補から旅の楽しみを考えてみたい。そう思わせた時点で、この取り組みは成功していると言えるだろう。ポイントの使い道に悩んでいる方は、ぜひ一度お試しあれ。







