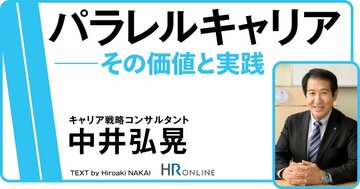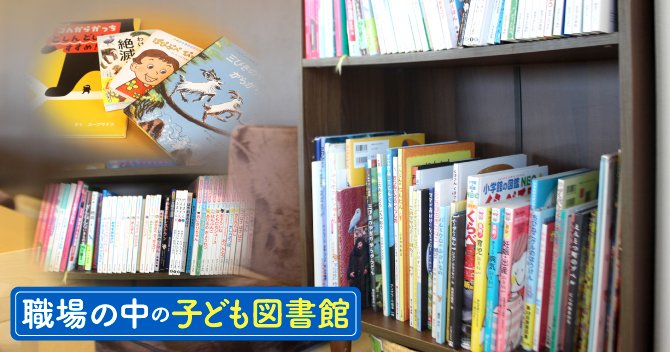
コロナ禍を経た、2020年代半ばのいま、人事・総務といったバックヤード系の業務は多忙を極めている。従業員の勤怠管理から福利厚生に至るまで、積み重なる案件に追われ、時間を効率的に使うことを余儀なくされながら、従業員の「働きやすい職場」づくりに腐心する人事・総務パーソンが多いようだ。そうしたなか、働く人の心と体を休める「リフレッシュルーム」に「子ども図書館」を設置した職場がある。弥生株式会社の大阪オフィス(大阪カスタマーセンター/大阪支社)だ。いま、なぜ、「子ども図書館」なのか? その企画・運営をおこなう森嶋綾子さん(人事本部・人事総務部)を訪ねた。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
「子ども図書館」は、絵本の数珠繋ぎプロジェクト
新型コロナウイルス感染症の「5類」への移行から2年以上が経った。緊急事態宣言発令期間の日常(*1)が、いまや、遠い記憶になりつつあるが、テレワークやマスク着用の常態化、オンライン教育やキャッシュレス決済の拡大など、“コロナ”は、私たちの働き方や生活スタイルに大きな変化をもたらした。
*1 第1回の緊急事態宣言発令期間は、2020年4月7日~5月25日。第4回が2021年7月12日~9月30日。
記憶に何よりも残るのは、職場の日常だった“対面でのコミュニケーション”が、コロナ禍では、非日常になったこと――弥生株式会社(以下、弥生)の森嶋綾子さん(人事本部・人事総務部)は、当時をこう振り返る。
「10年くらい前に、子育てをしている従業員でランチ会を企画して、2週に一度くらいの頻度で実施していました。スタート時はたった数人でしたが、ママさんだけではなく、(従業員である)パパさんたちも参加するようになって、20人くらいの規模になっていたのですが、コロナでなくなってしまいました……」
森嶋さんがランチ会を催したのは、当時のオフィス(大阪カスタマーセンター/大阪支社、以下、大阪オフィス)で、育休を取得して復職する従業員があまり多くなく、みんなでにぎやかに話して、悩みを打ち明けたり、情報交換したりするのがよいと思ったからだ。平日のランチ会だけではなく、休日に一緒に出かけたり、不要になった子ども服を譲り合ったり……幅広い年齢層の従業員同士がつながっていたという。
昨年(2024年)3月、弥生は、【大阪オフィスに「子ども図書館」が開設! ワーママ人事の経験から生まれた絵本の数珠繋ぎプロジェクト】という記事(*2)をオウンドメディアにアップした。そして、その「子ども図書館」の企画・運営をおこなっているのが、人事総務部に籍を置く森嶋さんだ。
*2 【大阪オフィスに「子ども図書館」が開設! ワーママ人事の経験から生まれた絵本の数珠繋ぎプロジェクト】(弥生株式会社 公式note/2024年3月28日)
コロナ前の、職場の従業員同士をつないでいた「ランチ会」と、コロナ後の、絵本の数珠繋ぎプロジェクトである「子ども図書館」は、どちらも森嶋さんの発案で、「コミュニケーション」の一手段と考えられる。「ランチ会」は、世間一般の職場で耳にするものの、オフィスにおける「子ども図書館」は聞き慣れない……まず、「子ども図書館」のきっかけを、森嶋さんに聞いた。
「もともと、住宅メーカーにいた私は、建築家の安藤忠雄さんが好きで、その安藤さんが、ここ(大阪オフィス)から徒歩10分ほどの場所に、“こども本の森 中之島(*3)”をつくりました。開館は、コロナ禍真っただ中の2020年7月。早速、私は、自分の子どもを連れて訪れました」
*3 こども本の森 中之島(大阪市北区中之島1-1-28/京阪中之島線「なにわ橋駅」3号出口すぐ)
当時、森嶋さんの9歳と6歳の子は、本や絵本に触れる適齢期だったが、コロナ禍ということもあって、“こども本の森 中之島”は完全予約制。なかなか入場できない状況のなか、親子で足繁く通ったという。
「市立の図書館だと、児童コーナーと大人の本のコーナーは別々の場所にあります。でも、“こども本の森 中之島”は、大人が読む本も子ども向けの本も混ざっていて、建築やデザイン系の、私が読みたいものもたくさんありました。子どもたちは、好きな絵本を次から次に手に取っていました」
“こども本の森 中之島”がある中之島公園には、国の重要文化財である大阪市中央公会堂といった観光名所的な場所もあって、子どもたちに建物を説明して歩いたことも、森嶋さんの忘れられない思い出になっている。「コロナ禍でいろいろたいへんでしたが、素敵な時間でした」と、子育てを懐かしむ。