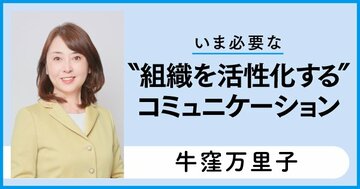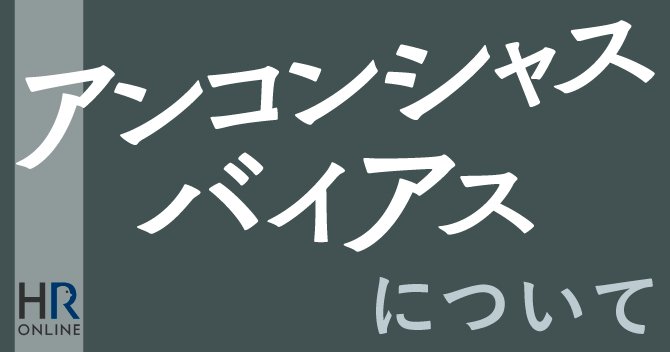
「あの人は育児中だから地方出張は嫌がるだろう」「外国籍の彼は日本人のマナーを理解しづらいにちがいない」――そんな思い込みで、対人関係にフィルターをかけてしまうことが職場で見受けられる。「無意識の偏見や思い込み」を「アンコンシャスバイアス」と呼び、企業・団体においては、「アンコンシャスバイアス」を研修によって理解し、減らしていく動きを進めている。そもそも、「アンコンシャスバイアス」とは何か? 働きやすい職場をつくるために心がけたいことは? 「アンコンシャスバイアス」のセルフラーニング動画から学んでみよう。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
セルフラーニング型の研修動画で学んでいく
2022年、私は、企業・団体の管理職・リーダーを対象にした「アンコンシャスバイアス研修」を受講して、その様子を「HRオンライン」でレポートした。「アンコンシャスバイアス」とは、「無意識の偏見や思い込み」を意味し、自分でも気づかないうちに他者を属性で括ってしまったり、思い込みによる発言で相手に不快感を与えてしまったりする言動を指す。当時、私はほとんど知識のなかったアンコンシャスバイアスについて、研修を通して知識を得て、“アンコンシャスバイアスは、誰もが持っているものだからこそ、うまくつきあっていく”という姿勢を学んだ。
それから3年――いま、多くの企業が「アンコンシャスバイアス研修」を取り入れ、組織やチームにおけるアンコンシャスバイアスの理解を急いでいる。

併せて読みたい!
企業向けの「アンコンシャスバイアス研修」を受けて、私がわかったこと
狩野南 (「HRオンライン」2022年4月21日配信)
「アンコンシャスバイアスへの気づきは、 ひとりひとりがイキイキと活躍する社会への第一歩」――これは、内閣府男女共同参画局の広報誌「共同参画」の昨年2021年5月号の特集タイトルだ。「無意識の偏見・思い込み」を意味する「アンコンシャスバイアス」。「文系出身の社員は計算が苦手だから…」「女性社員は子育てがたいへんだから…」といった思い込みが円滑な対人関係に水を差すこともあるが、はたして、そうしたアンコンシャスバイアスを企業内の組織において減らす方法はあるのだろうか? 管理職・マネージャー向けの「アンコンシャスバイアス研修」を受けて、考えてみた。
今回、私が視聴したのは、一般社員向けのセルフラーニング型の研修動画「アンコンシャスバイアスの対処法」だ(*)。計7本の短い動画から成り、立教大学経営学部の中原淳教授と武蔵野大学グローバル学部の島田徳子教授がわかりやすく解説していく。
研修動画の開発担当者である広瀬一輝さん(ダイヤモンド社/HRソリューション事業室)に制作の背景を伺った。
「管理職を対象とした『アンコンシャスバイアス研修』を開発した後、複数の企業から、一般社員も学べるコンテンツを求める声をいただきました。もちろん、『アンコンシャスバイアス』は、管理職に限ったテーマではありません。中原教授と島田教授の監修のもと、一般社員向けに講義内容や表現などを工夫して、セルフラーニング型の研修動画を制作しました」(広瀬さん)
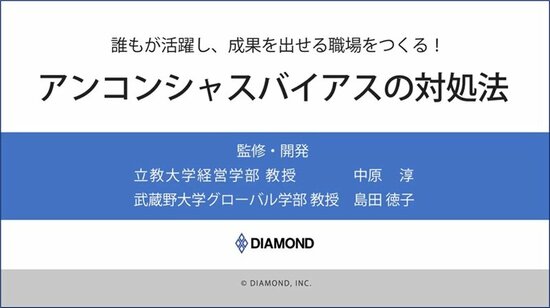 セルフラーニング型研修動画「アンコンシャスバイアスの対処法」より
セルフラーニング型研修動画「アンコンシャスバイアスの対処法」より詳しくはこちら
リアル(対面)やオンラインで行う「アンコンシャスバイアス研修」の場合はファシリテーターが必要だが、セルフラーニング型の研修動画「アンコンシャスバイアスの対処法」は、いつでもどこでも、自分の好きな時間に視聴して、学ぶことができる。その点をプラスと感じながら、早速、私は動画を再生した。
1本目は、「オープニング」と題され、学習テーマの確認、身近に潜むステレオタイプや偏見の確認、教材の全体像について、中原教授が説明していく。自分では偏見は持っていないつもりでも、ステレオタイプの事例として紹介された会話を聞くと、確かに、「無意識に」言ってしまいそうな言葉が多いと痛感した。特に昨今は、行き過ぎた言動を「ハラスメント」と捉えられるケースが増えているだけに、ついつい身構えてしまいがちだが、中原教授は、「アンコンシャスバイアスは誰もが持っているもの。気づいたうえでうまく付き合っていく方法を学びましょう」とメッセージする。アンコンシャスバイアスをゼロにするのではなく、自分でコントロールして減らしていく――それならできるのでは?と、私の気持ちは少し楽になった。