東急のほとんどの路線が
20以上も順位を下げた背景
東部も似た傾向だ。JRは総武線快速こそ11位に入っているが、総武線各駅停車、京葉線とともに輸送量が同2割以上減少している。また、総武線各駅停車と相互直通運転を行う東西線も依然、混雑路線ながら2019年度の199%(1位)から150%(15位)に大幅下落している。
一方、総武線と東西線の間を走る都営新宿線は輸送量がほぼ横ばいで、30位から16位に上がっている。これはJR線、東西線が千葉県からの利用が多いのに対し、都営新宿線の中心は都内(江東区、江戸川区)にあるためと考えられる。
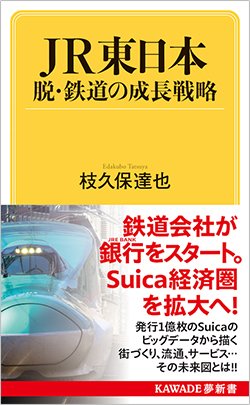 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
北西部は北東部と同様、需要が底堅い。大江戸線の他にトップ20に入る路線はないが、ピックアップした5路線はいずれも対2019年度の輸送量増加率がトップ20入り。都営三田線と西武池袋線は横ばいで、その他は順位が上がっている。西部も中央線各駅停車を除き輸送力の減少率は相対的に低く、順位も横ばいだ。
先ほどの図で示した通り、南西部は下落が大きい。特に東急は先ほどの図で示した通り、主要路線がいずれも20以上順位を落としている。コロナ禍以降も輸送力増強を緩めなかった東急の「経営努力」も大きいが、沿線住民にテレワークなど多様な働き方が普及したことで、朝ラッシュへの集中が緩和した結果と考えられる。
最後に南部だが、東海道線と京浜東北線が10位以内に入っているものの、全体的に見れば輸送量は大きく減少していることが分かる。特に横浜線、横須賀線、根岸線及び京急線といった横浜以遠の減少が著しい。
全体的に見ると方面別に加え、23区内外、また大宮、千葉、横浜など都心30キロ圏内外で傾向が異なりそうだ。2024年度のJR各駅の定期乗降人員が発表されれば検証してみたい。







