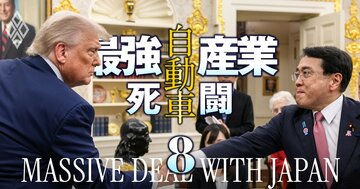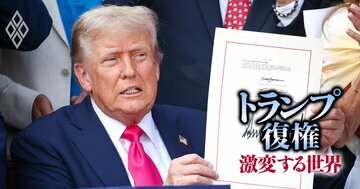衆院本会議前に会話する石破茂首相(左)と赤沢亮正衆院議員=8月1日 Photo:SANKEI
衆院本会議前に会話する石破茂首相(左)と赤沢亮正衆院議員=8月1日 Photo:SANKEI
不透明な部分残る日米関税合意
短期と長期の対応の両面が必要
日米関税交渉が急転直下で合意した。25%が適用される予定だった「相互関税」は15%となり、7月31日にはトランプ大統領が大統領令に署名した。さらに最大の焦点だった自動車関税も15%に引き下げられることになった。
一方で、関税引き下げの見返りに、日本側は5500億ドル(約81兆円)を上限にした公的な金融支援で、日本企業による米国への投資を後押しするほか、米国からのコメの輸入拡大や農産物や航空機の購入などが盛り込まれた。コメや農産物について日本が関税を新たに下げることはないという。
日米政府の説明にずれがあり、なお不透明な部分は残るが、関税交渉はひとまずは妥結し、日本経済への悪影響も深刻なものとはならない関税率となり、一定の評価をすることはできる。
だが、今回の合意は大筋合意であり、法的文書はまだ締結されていない。
さらに、合意文書の中には「再び関税を上げない」との条項が盛り込まれておらず、実務交渉が進まない場合、関税率が引き上げられるリスクがある。
日本政府はまずは、日本経済にさらなる悪影響が出ることがないように、米国に合意文書の作成や大統領令発令などによる着実な履行を求めるとともに、国内への影響を緩和する政策対応が必要だ。
だがより重要なのは、中長期をにらんだ米国との関係の再構築だ。米国政治はこれまで80年サイクルで動いてきており、トランプ政権が打ち出した自国第一、孤立主義回帰は今後も長く続くと考えられる。
米国の政治姿勢が長期的なスパンで見た歴史的転換点を越えたと考えられるなか、日本の米国との付き合いも練り直しが必要だ。そのキーワードは「二正面作戦」だ。