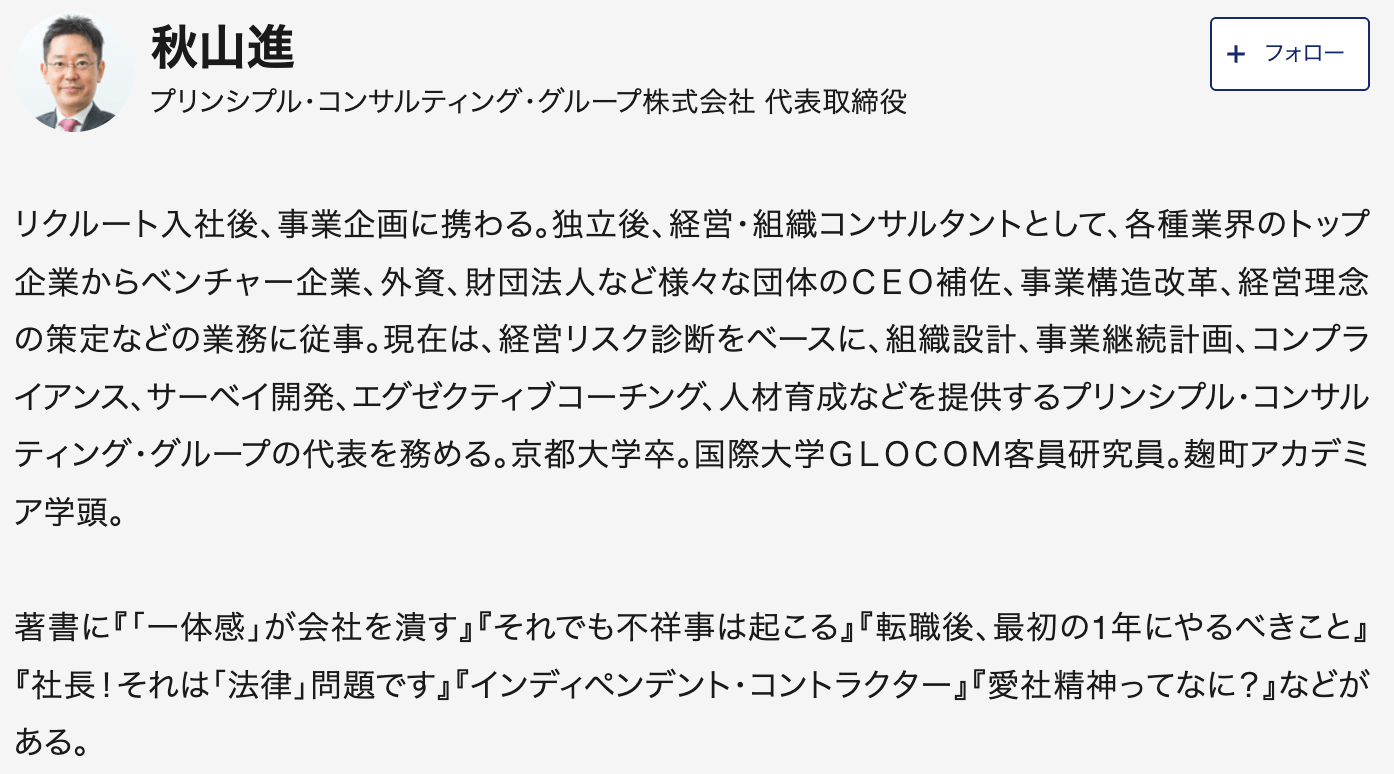いかにして、さまざまなタイプの人々を一度に巻き込むか
まず大前提として、「全員を同じように集中させる」ことを狙ってはいけない(それはどだい無理な話である)。
真の巻き込みとは、それぞれ異なる参加モードに合わせた接続点を用意し、異なる形で内的な関与を引き起こすことにある。そのための語り方や構成には、次の3層構造が有効である。
冒頭例に挙げた、孫正義氏のスピーチをはじめ、身近な人、著名人で話がうまいと思う人のスピーチなどを思い浮かべながら読んでいただければ幸いである。
第1層:情動レベルの働きかけ(いわゆる「エモ」さを喚起する)
•ストーリー、笑い、驚き、問いかけなど
共鳴予備軍・形式参加・離脱予備軍を揺さぶるための導火線
•ストーリー、笑い、驚き、問いかけなど
共鳴予備軍・形式参加・離脱予備軍を揺さぶるための導火線
第2層:構造的・知的提示(「こうだから、こうなる」)
•ロジック、因果、データ、対比
探索型・受動吸収・選別評価モードに対応
•ロジック、因果、データ、対比
探索型・受動吸収・選別評価モードに対応
第3層:実践接続の提示(「こんな風に使える」)
•事例、フレームワーク、チェックリスト
実践型・懐疑・自己防衛モードに「価値」を伝える
•事例、フレームワーク、チェックリスト
実践型・懐疑・自己防衛モードに「価値」を伝える
また、参加者の一部に反発的・離脱的なモードが存在したとしても、力でコントロールしようとしては逆効果である。代わりに設計と余白で対応する。
• 発言以外の参加も許容(メモ、うなずき、ワークシートなど)
• 質問の形式を多層にする(感情、事実、意見など)
• 異論の可能性を先に明示する(「納得できない方もいると思います」と譲歩を示すなど)
• 質問の形式を多層にする(感情、事実、意見など)
• 異論の可能性を先に明示する(「納得できない方もいると思います」と譲歩を示すなど)
その場に応じて、上記の3層アプローチにおける時間やエネルギーの配分バランスを調整して変えていくことが重要になる。全部のタイプに目配りをしながら、今はどのアプローチをしているのかを自覚的に意識し、話を進めるのである。
とはいえ、すべての聴衆を完全に掌握することは不可能である。よって、できることは最善を尽くすことであり、
• 誰かの心に種をまく
• 興味を引く
• 違和感を残す
• 最後に回収する
• 興味を引く
• 違和感を残す
• 最後に回収する
こうした行為を積み重ね、「巻き込み」を実現するのである。
以上、意識して練習すれば、身に付けられるテクニックのようなものを紹介した。ただし、リーダーやファシリテーターに求められるのは、「自分の語りを聞いてほしい」ではなく、「あなたがそこにいてくれることに意味がある」と伝える力であることを忘れてはならない。
その包摂的な姿勢こそが、これからの時代の対話的リーダーにふさわしい資質であり、場を動かす真の能力なのだ。
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)