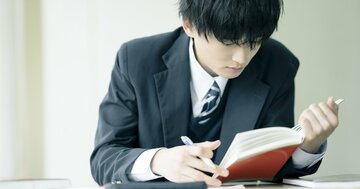写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
京大までいけば、エリートコースまっしぐら。そんなふうに思われがちだが、その後に躓いて学歴を無駄にしてしまう人は少なくない。いっぽうで、大学を通過点にして、社会人として大きく飛躍する人もいる。同じ大学、同じ学力だったはずなのに、なぜ差がつくのか?京大で出会った2人の男を通して、その決定的な違いを探る。※本稿は、佐川恭一『学歴狂の詩』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。
京大には入ったけれど
目標を見失っていた2人
私は文学部(編集部注/京都大学)の同じクラスに自分にかなり似たタイプの受験狂がいるのを見つけた。その男の名は野々宮、九州の有名スパルタ進学校出身で1浪だった。
関西に住んでいなかったせいか私よりはるかに強烈に京大に憧れていたようで、「絶対に鴨川をチャリで渡って通学したい」というアホな理由で、わざわざ百万遍の(編集部注/京都大学吉田キャンパスのある地域)近くでなく同志社に近い今出川に部屋を借りていた。
しかも織田裕二の超絶ファンで、『踊る大捜査線』の青島と同じコートを季節外れの時期にもよく着ており、こいつは本物のアホなのだと私は思っていた。
そんな彼はかなり大きなお寺の息子で恐ろしいほどの金持ちだったので、借りている部屋も信じられないほど広く、しかも人との間に壁をまったく作らない人間性も持ち合わせていたため、だんだんみんながそこに集まってゲームをしたり酒を飲みまくったりするようになっていった。
私たちは3回生になる時に専攻を選ばされたが、私と野々宮は2人とも文学部の「社会学専修」というコースに入った。