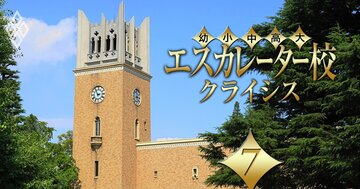Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「受験人口の減少が階段の踊り場状態にある間、入試難易度の易化が緩やかになるかもしれない」と河合塾教育研究開発本部の近藤治主席研究員は言う。ということは、そのタイミングにぶつかる現高校2年生までは大学受験で「貧乏くじ」を引かされてしまったのか。連載『教育・受験 最前線』では、連載内特集『大学入試2026』を10回以上にわたってお届けする。第6回は首都圏の難関私立大学群「GMARCH」(学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)の44年間の偏差値推移データも一挙掲載し、受験難易度の変化に迫る。(ダイヤモンド編集部副編集長 臼井真粧美)
現高校2年生までは「貧乏くじ」?
入試難易度の易化が緩やかに
2025年度入試(25年4月入学)について、「特に私立大学の入試難易度の易化現象がパタッと止まった」と河合塾教育研究開発本部の近藤治主席研究員は振り返る。
首都圏の最難関私立大学群「早慶上理」(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学)、難関私立大学群「MARCH」(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)、「成成明國武」(成蹊大学、成城大学、明治学院大学、國學院大学、武蔵大学)、中堅私立大学群「日東駒専」(日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学)の4つの大学群で見ると、25年度一般選抜入試の倍率(志願者数÷合格者数)は、各大学群共に24年度と比べて上昇した。関西の難関私立大学群「関関同立」(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)、中堅私立大学群「産近甲龍」(京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学)の2つの大学群も同様だ。
倍率が上昇したのは志願者数の増加と、合格者数の減少によるもので、複数の要因が重なった。志願者数が増えた背景として、大学入学共通テストで新課程がスタートする年だったために国公立大学志願者が保険をかけて併願校数を増やした。合格者数が減った背景には、一般選抜枠から年内入試枠に定員がシフトしたことなどがある。
それとは別の要因として上がるのが、18歳人口の“増加”だ。
少子化が加速し、18歳人口は減少期に入っている。しかし、25年度からの3年間に限っては話が変わってくる。24年度入試に106.3万人だった18歳人口が、25年度は109.1万人、26年度は109.3万人、27年度は108.5万人と膨らむ。大学進学率も頭打ちなので、26年度を境にその後は18歳人口も大学進学者数も右肩下がりになっていく見通しだ。
ということは、24年度に比べると、25~27年度の受験生、言い換えれば現高校2年生までは競争相手が増えて受かりにくくなる要因が一つプラスされる。前出の近藤氏は「受験人口の減少が階段の踊り場状態にある間、入試難易度の易化は緩やかになるかもしれない」と言う。
25~27年度の大学受験生は、強制的に「貧乏くじ」を引かされてしまったのか。次ページでは、MARCHに学習院大学を加えた「GMARCH」の44年間の入試偏差値の推移データも一挙掲載し、受験難易度の変化に迫る。