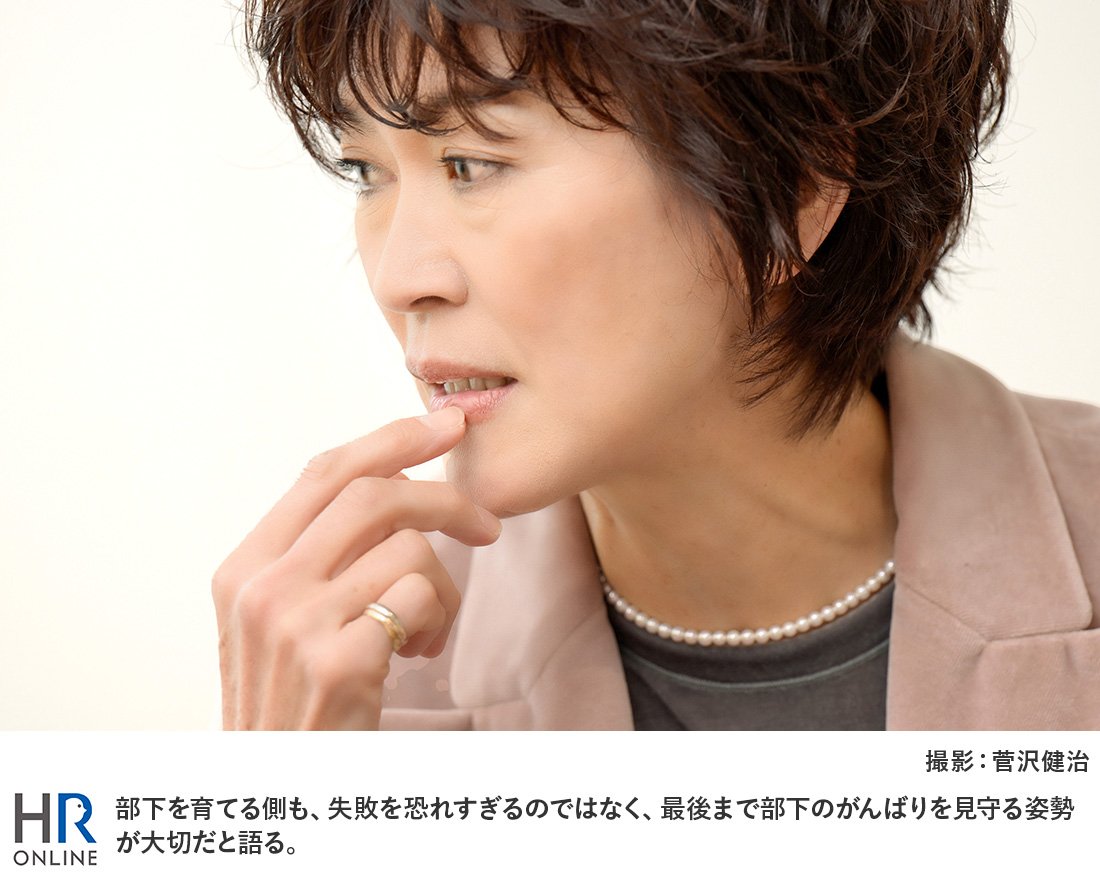一度スタートしたら、ゴールまで走ることが大切
有森さんは、「何があっても諦めない」という姿勢を貫いている。昨今、物事がうまくいかないと簡単に投げ出してしまう若者も多いが、その理由はどこにあるのだろう? 「途中で投げ出さない」という姿勢は、どうしたら育まれるのだろう?
有森 最近は、「嫌(いや)なら、やめてもいいよ」「無理にがんばらなくても大丈夫だよ」といった声かけで育てられ、自分に何ができて、何ができないのかがわからないまま、次の行動に移っていく子が多いように感じます。自分がどうしたいのかがわからないため、粘らずに諦めてしまう若者が増えているのではないでしょうか。自分でスタートしたのなら、できるだけ、自分でゴールまでいくべきだと、私は思います。そこで初めて、自分にできるのかできないのか、自分に向いているのか向いていないのかという気づきが生まれますから。
組織における部下の育成では、「(部下に)失敗されたら取り返しがつかない」と慎重になってしまい、部下がゴールにたどり着くまで任せきれない上司も多いだろう。
有森 そもそも、私は「失敗」という言葉が嫌いです。たいしたことでなくても、「失敗」と名付けた途端に失敗になってしまう。たとえば、「ブランク」という言葉もそう。日本人は「ブランクができてしまった」と言いますが、海外の人は「いいブレイクができたね」と、その人に声をかけます。ネガティブな言葉にとらわれると、動けなくなってしまうこともあるでしょう。上司は「失敗」を不安視するより、部下にいろいろな機会を与えて、どんな状況になろうとも、がんばっている姿を最後まで見届けられるといいですね。