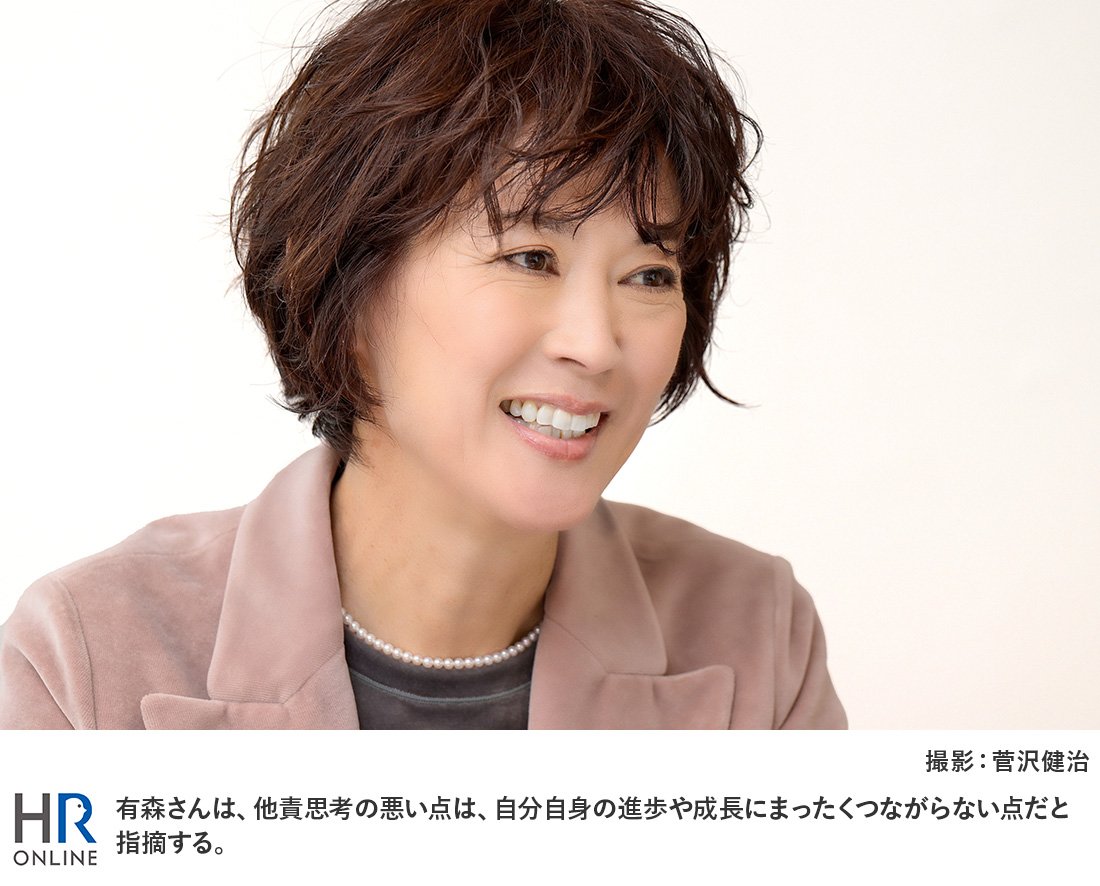“他責”な考え方と、“自責”で考える人の違い
有森さんのお話からは、何事も他責にせず、自分で受け入れてきた軌跡が見えてくる。人は、日常生活や仕事をするうえで、ついつい、他責な考え方になりがちだ。たとえば、昨今、希望どおりの部署に配属されるかどうかを“配属ガチャ”と言い、「仕事がうまくいかないのは、“配属ガチャ”が外れたからだ」などと嘆く新入社員がいる。
有森 他責思考の人は、「他人が何を与えてくれるのか?」を基準に物事を考えます。すると、入社を決めたのも、仕事にコミットしているのも自分なのに、「自分の意志でここにいる」という意識が薄くなる。結果、何かが起きるたびに、「良い部署に配属してくれなかった会社が悪い」といった考えにとらわれるのです。うまくいかないことを他人のせいにしたらラクですよね。でも、他責の考え方の中には、“自分”がないから、その人自身の進歩や成長はありません。自分の思いひとつで、才能を活かしたり、周りの人と変化を起こせたりしていけるはずなのに、他責思考はそうした可能性を捨ててしまっています。
他責ではなく、“自責”で生きるには、「自分の頭で考えること」が欠かせない。いま、有森さんは指導者として、自分の頭で考えられる人物を育成するために、子どもや若者たちに接している。
有森 たとえば、靴のかかとを踏んでいる子、玄関に靴を脱ぎ捨てる子がいます。そんなとき、「いま、地震が起きたら、自分の靴をさっと履いて逃げられる?」と、私はその子に考えさせます。靴がバラバラだったら、自分の靴をぱっと見つけることはできないし、見つけても、かかとが潰れていたら、履いた靴がすぐに脱げてしまいます。「なぜ、ダメなのか?」をしっかり考えられれば、同じことを繰り返さないようになります。ただ、こうしたことは、子どもと毎日一緒にいる人が言ってもなかなか伝わりません。たまに会う指導者が言うからこそ、強い効果があるのです。職場でも、直属の上司や先輩だけではなく、いろいろな役割を持った人が、一人の新入社員に関わっていくことが大切だと思います。