そこに夏目漱石がいて、夏目漱石が自分に共感してくれていると考えると、世間の人たちの言うことよりも漱石が言うことのほうが確かなんじゃないかと思うこともできます。あるいは本ではなく、芸術作品や音楽でもいいでしょう。
世間と離れたところに自分なりの読書空間をつくり、そこに帰るといちばん落ち着けるようになるということを、私は中学生ぐらいからずっとやっていました。まわりの人が何を言っていても、自分は勝海舟や漱石と対話するからいいんだという気持ちでいたところ、それがいい練習になっていつも心の中に避難所がある状態になりました。
まわりで嫌なことがあったときにはさっと家に帰って太宰治でも読むと、彼は普通の会社員とは全然違う観点で生きていますから、そこはそこで心がゆるむということがあります。あるいは、ココ・シャネルの本を読んだら心が励まされる人もいるでしょう。
そういった読書部屋のようなものを心の中につくっておいて、外でのストレスをそこで回収、吸収していくという仕組みです。それは精神の安定にはものすごく効果があるので、そういう意味を込めて「心にいつも地下室を」と言っているのです。
ストレスで乱されないために
心に「内なる港」をつくろう
その読書空間で先人と対話をするということを習慣化すると、外の世界の意見がどちらでもいいように思えてくることがあります。生活していくうえでは、外の世界の人のことももちろん尊重しますが、そこで誰が何を言っていても本当のところは大して影響ないというように、心の中で港をつくっておくという感じでしょうか。
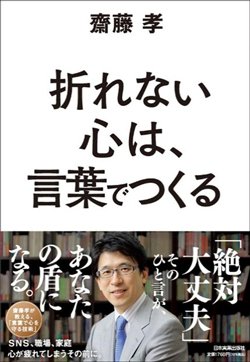 『折れない心は、言葉でつくる』(齋藤 孝、日本実業出版社)
『折れない心は、言葉でつくる』(齋藤 孝、日本実業出版社)
外海がいくら荒れていようとも、駿河湾の中の焼津港は湾の中の港なので荒波を防ぐことができるというような感覚で、防波堤的なものを心の中に持つということです。
それが、家族であることもあるでしょう。家族との関係は、外の基準とはちょっと異なるものです。そのように、外で何があっても中はまあまあ平和だという空間をつくっていくと、心の安定が図れるようになります。
実際の家族が安らぎにならないこともあると思いますが、その場合は、いつも安心して語り合えるような精神的なファミリーというものをつくっていくことが大事だと思います。







