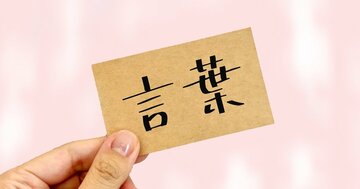写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
文章を読んだとき、「分かりやすい」ものと「分かりにくい」ものの間にはどのような違いがあるのだろうか?説得力のある文章を書くには、まずはこの差の原因を理解することが大切。認知心理学的な視点から、分かりやすい文章に必要なポイントを考えていこう。※本稿は、藤沢晃治『「分かりやすい文章」の技術 新装版 読み手を説得する18のテクニック』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。
入ってくる情報を
審査する「脳内関所」
認知心理学という学問があります。人間が外界からの情報にどのように気づき、解釈し、思考していくかを研究する学問です。その認知心理学の知識を借りて、「分かりやすい」という意味を考えてみましょう。
「分かりやすい」の前に、「分かる」とは、そもそもどういうことなのでしょうか。
認知心理学では、人間が外界からの情報を処理する際、情報が最初に処理される場所を短期記憶(一次記憶)と呼び、短期記憶で処理した情報が最終的にしまわれる場所を長期記憶(二次記憶)と呼んでいます。
短期記憶は、情報が一時的に通過するだけの場所です。記憶を保持できる時間は秒単位で、たとえば電話番号をメモしないで覚えていられる程度の時間です。記憶できる情報のサイズも小さく、文字にして10文字程度です。
短期記憶では外部からの情報をチェックし、長期記憶にしまわれている過去の記憶と比較して同じものを探したりする作業が行われます。そこで私は、短期記憶を分かりやすく「脳内関所」と呼んでいます。目から入ってくる文章も、最初にこの脳内関所で審査を受けることになります。