
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1969年1月20日号に掲載された特集『国内大手の外資対策を解剖する』の記事「外資攻勢の矢面に立つ洋酒・清涼飲料業界」を紹介する。当時、ウイスキーなどの洋酒業界では自由化が秒読みの段階に入っていた。実際、69年には米国産のバーボンが、2年後の71年には英国産のスコッチウイスキーの輸入が自由化され、舶来ウイスキーブームが起きた。ブランド力のあるスコッチと資本力のあるバーボンの脅威を前に、国内市場を寡占化したサントリーとニッカウヰスキーという二大メーカーや下位メーカーはどう対抗しようとしていたのか。記事は、“第二次洋酒戦争”前夜の日本の洋酒業界の最前線をレポートしている。(ダイヤモンド編集部)
洋酒業界に輸入自由化の衝撃
スコッチとバーボンが上陸へ
“スコッチ”がやって来る。“バーボン”が上陸する――。いま洋酒界は、自由化の話題で持ち切りになっている。当初、業界では、自由化の時期を、1972~73年と考えている人が多かった。4~5年のうちには、なんとか外資遊撃体制が整えられる。自由化には、各社が私欲を乗り越えて反対を続けてきた。
ところが、その自由化が大幅に早まることになったのだ。洋酒自由化のスケジュールは、次のようなものである。まず、この4月1日にはスコッチウイスキーの資本自由化が行われるもようだ。外資側の出資比率を50%まで認める第二種業種にリストアップされる。続いて10月1日には、米国の大衆ウイスキーともいうべきバーボンウイスキーがやはり50%自由化となる予定である。
まだある。以上は資本の自由化であるが、貿易の自由化も並行して行われる。10月1日にはブランデーの貿易自由化がスケジュールに上っている。これに続いてスコッチの原酒(モルト)の自由化が70年春、バーボンの貿易自由化もこのころには実施される気配が強い。
急転直下、矢継ぎ早の自由化攻勢である。
酒類は多額の酒税を課せられているため、その酒税確保の建前から、事業は監督官庁の免許下に置かれている。一種の免許事業である。しかも、この免許は新規にはなかなか交付されない。業者の乱立過当競争から、既存メーカーの納税能力が低下することを役所が懸念しているからである。
国内の大手会社は、新工場の建設に当たって、既存メーカーの免許を買収するという手段を取っている。ここに、酒類業界の非近代的な一面があるのだが、それはそれとして、外資会社といえども日本市場への本格進出に当たっては、この事業免許を取得しなければならない。
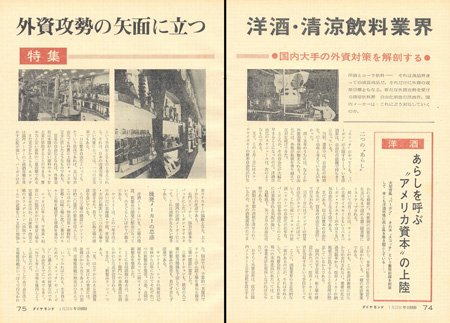 「ダイヤモンド」1969年1月20日号
「ダイヤモンド」1969年1月20日号
おそらく外資会社は、既存の国内メーカーと合弁会社を設立するという手段を取るものと考えられる。それは、日本の流通市場に疎い外資にとっては、一つの安全策でもある。
一口に資本自由化と言っても、そういう状況であれば、50%自由化でも外資に上陸のチャンスを完全に許したようなものである。貿易の自由化となれば、外資会社は本国から安い原料やモルトを大量に供給することができる。資本力と安い原料の二重攻撃である。
また見方を変えると、スコッチは国内メーカーの上級酒市場を脅かす心配が強いし、バーボンは大衆ウイスキーの強敵となる。上と下からの圧迫である。名門スコッチと、強力な資本をバックにしたバーボンウイスキー――。国内の洋酒メーカーにとって、これは油断のならない相手である。
洋酒メーカーはいま、工場の増設、新製品の開発に懸命になっている。目まぐるしいばかりの動きである。サントリーは、この1年半ほどの間に北海道千歳、愛知県犬山に相次いで二つの新工場を完成させた。目下、広島工場の建設を急いでいる。







