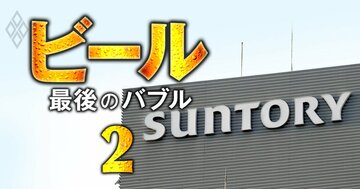Photo:Keystone/gettyimages
Photo:Keystone/gettyimages
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「週刊ダイヤモンド」1970年4月20日号の記事『ビールに呑まれたサントリー〈赤字転落?〉――回生への“手”は万全か…』を紹介する。1970年、サントリーは新たな戦略を打ち出した。海外の洋酒メーカーに加え、異業種の武田薬品工業や不二家などと相次ぎ提携に踏み切ったのだ。販売会社としての色を強める「脱・メーカー作戦」ともいえる動きの背景には、二つの危機の存在があった。“天敵”との提携のうわさが上がるほど、サントリーが従来の方針を大転換したのはなぜか。記事では当時のサントリーの財務などの分析も併せ、サントリーの苦境を解説している。(ダイヤモンド編集部)
サントリーがスコッチの「大物」に接近!?
海外の洋酒大手や武田薬品と相次ぎ提携
サントリーが、スコットランドのDCL社に“秋波を送っている”といううわさがある。DCLのフルネームはディステラーズ・カンパニー・リミテッド。何を隠そうジョニーウォーカー、ホワイトホース、B&Wなど名門スコッチのブランドオーナー、総販売元である。スコッチ市場の70%を押えている大物だ。
サントリーとDCLの接近説……これは、はなはだ穏やかでない。というのは、この話、うわさの相手が大物というだけではない。サントリーは、つい最近までスコッチの上陸を“天敵”の来襲のようにわめきたて、反対に次ぐ反対を続けていたからである。酒類界で、スコッチの輸入自由化を正面切って反対してきたのはサントリーだけであった。
洋酒界一般の空気としては、自由化は避けられないものとし、むしろそれを機として外資と手を組んで巻き返しに出ようとする会社が多かった。事実、多くの会社がDCLなど数社と交渉を持った。サントリーでは、DCL問題については、固く口を閉ざしている。果たして、DCL社との話がどこまで進んでいるのか、それはもう少し様子を見なければ、分からない。
しかし、それはそれとして、ここへきてサントリーの動きに、これまでとは違った変化が出てきたことは確かである。
その第一は、去る3月、米国のバーボンウイスキー2社と、フランスのコニャックメーカーとの販売提携である。契約を結んだ相手は、バーボンがシェンレー社およびブラウンフォーマン社、コニャックがマーテル社である。
シェンレーは、バーボンビック4の一つに数えられるマンモス企業であり、マーテル社はフランスではコニャックブランデーのトップメーカーである。今回は、3社の代表商品の中から合計9銘柄を選び、サントリーが輸入販売しようというのだ。
バーボンは、米国ではスコッチと市場を二分するほどの力を持ち、大衆酒としてはスコッチを上回る人気を集めている。
スコッチが高級洋酒であれば、バーボンは大衆酒の先兵として、日本市場への浸透が予想される商品である。バーボンは、スコッチに先駆け、すでに1969年4月に輸入が自由化された。その結果、69年のバーボン輸入量は前年の3倍半に急膨張している。サントリーは、そのバーボンの大手メーカーと手を結んだのである。
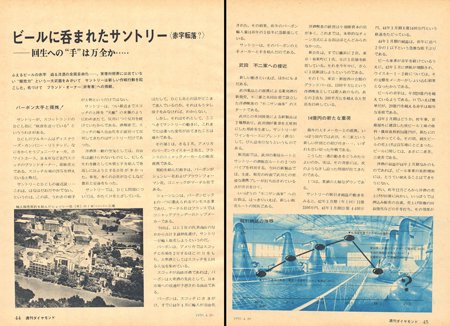 「週刊ダイヤモンド」1970年4月20日号
「週刊ダイヤモンド」1970年4月20日号
新しい動きといえば、ほかにもまだある。武田薬品工業との提携による薬用酒の新発売、不二家と共同出資で設立した洋酒喫茶の“不二サン商事”のスタートである。