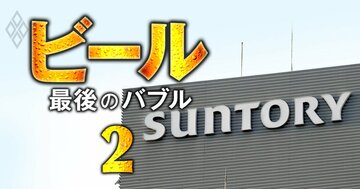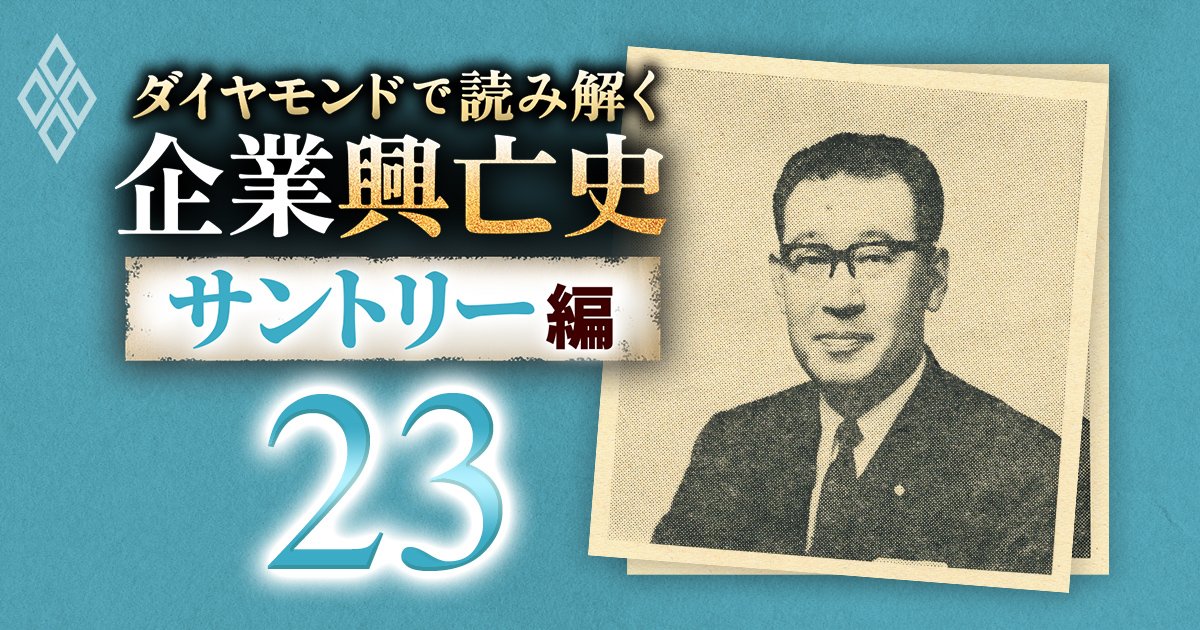
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1968年6月24日号に掲載された『京都・新工場にかけるサントリー――ハイペースのビール設備増強』という記事を紹介する。サントリーは67年に発売した純生ビールの大ヒットの波に乗り、京都工場の新設など大型の設備投資を矢継ぎ早に仕掛けていた。当面の大赤字経営も覚悟の上で、サントリーが攻めの姿勢を続ける背景には、実は目先に迫り来る危機の存在があった。(ダイヤモンド編集部)
サントリーが純生で好調も
酒税増の影響で伸び率悪化
今年(編集部注:1968年)は“純生”発売2年目を迎え、その真価が問われている。現段階では昨年ほどの勢いはないが、東京・武蔵野工場の増設に引き続き、京都・新工場の建設を推進し、一気に勝負に出る。
サントリービールの年初の滑り出しは、非常に順調であった。1月と2月が良く、3月はちょっと落ちたが、本年1~3月の出荷は、前年同期間に比べて2.1倍という好調さであった。4月も、悪くはなかった。麒麟の56%増、朝日の37%増、サッポロの30%増に対し、サントリーは83%増であった。
しかし、5月に入って、やや事情が変わっている。5月の出荷は、麒麟の43%増、朝日の20%増、サッポロの8%増、サントリーは18%増という数字になっている。
サッポロは、昨年、5月の中~下旬から出荷が大幅に伸びた。その関係で、サッポロは5月の数字が落ちているが、サントリーも5月は18%増と従来よりは伸び率が落ちている。サントリーも、昨年は“純生ビール”が5月に入ってから大当たりした。今年5月の伸び率が悪いのはサッポロと同じ理由によるわけであるが、さらに、もう一つの促進事情がある。
それはビールの値上げである。ビールは、5月1日から酒税が引き上げられ、大瓶の小売価格は120円から127円になった。これと前後して、業者側からも1本について3円の値上げ案が打ち出され、値上げ前に手当てしようという猛烈な“駆け込み需要”が起こった。
当然、こういう場合はシェアの高い銘柄に注文が集まる。サントリーがシーズンに入って、やや伸び率が悪かったのは、この事情が影響している。昨年は“純生”を発売して一気に波に乗せたが、今年はビール税引き上げ=再値上げ気運にやや邪魔された形である。これから最盛期を迎えて、サントリーがどの程度の伸び率を見せていくか。目先的に言えば、そこがやはり一つの焦点であろう。
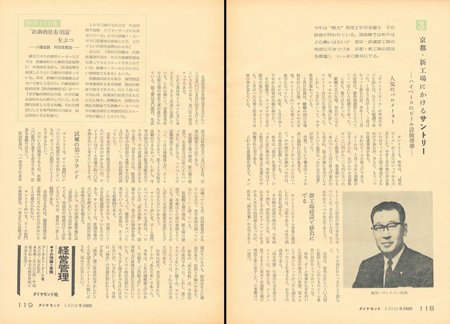 「ダイヤモンド」1968年6月24日号
「ダイヤモンド」1968年6月24日号
サントリーがビール事業に進出したのは、1963(昭和38)年である。今年で満6年目を迎える。その間の出荷の伸びは、64年47.4%、65年57.8%、66年は冷夏と不況のダブルパンチを受け5.5%の出荷減となったが、昨年は“純生作戦”が大当たりを取り、その遅れを一気に取り戻した。
出荷は、前年に比し2.08倍に膨張した。このときのビール業界におけるシェアは3.2%。昨年、ビール事業から手を引いた宝酒造が過去10年間、営々として築いたシェアが2%に満たなかったことを考えると、かなりの成長である。
“純生作戦”の成功に力を得たサントリーは、昨年8月、シーズン終了を前に東京・武蔵野工場の増設工事に着手した。工事費は11億円。生産能力を年間9万キロリットルから13万5000キロリットルに引き上げようというものである。50%の能力アップである。