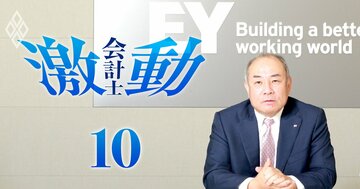写真:つのだよしお/アフロ
写真:つのだよしお/アフロ
AI議事録で脚光を浴び上場したオルツの不正会計は、東京地検特捜部が10月9日、元社長ら4人を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕する刑事事件に発展した。同社は、売上債権や在庫の膨張では見抜きにくい“資金の循環取引”で決算を偽装。偽装の兆候はどこに表れていたのか。長期連載『スタートアップ最前線』で、オルツ不正会計の真相に迫る。(ダイヤモンド編集部編集委員 竹田孝洋)
元社長ら逮捕で刑事事件に発展
巧妙だった「資金循環」スキーム
請求書やメールの書き換えなどで、循環取引への疑念をベンチャーキャピタル(VC)や主幹事証券、東京証券取引所の上場審査部に抱かせないようにしてきたオルツ。その巧妙な手口について、ダイヤモンド編集部は今月8日、『AIスタートアップ「オルツ」上場廃止の真相、巧妙な“資金循環取引”で監査法人や東証を欺いた手口』で詳述した。
翌9日、同社元社長の米倉千貴容疑者や前社長の日置友輔容疑者ら4人が金融商品取引法違反容疑で逮捕された。同社の2021年12月期以降の売上のほとんどが、循環取引による架空計上だったのである(下図参照)。
通常の循環取引であれば、自社から複数社を経由して再び自社が製品を買い戻す過程で、購入価格が積み上がる。その結果、在庫または売上債権が膨張しやすい。
結果として、売上債権回転日数や棚卸資産回転日数が増加することが多く、そこに不正会計の前兆をかぎ取れる場合がある。
しかしオルツの場合、循環しているのが「製品」ではなく「資金」だった。そのため、売上債権回転日数と棚卸資産回転日数は、大きく膨らんではいない。
公表財務諸表から計算される23年12月期と24年12月期の売上債権回転日数/棚卸資産回転日数は、それぞれ51.20日と59.72日、19.01日と17.63日である。
売上債権回転日数は増加しているものの、情報通信業の平均は45~60日前後で、特段大きいわけではない。一方、棚卸資産回転日数はむしろ減少している。
それでは、どこに不正会計の兆候が表れていたのか。次ページでは、オルツの財務指標を分析していく。