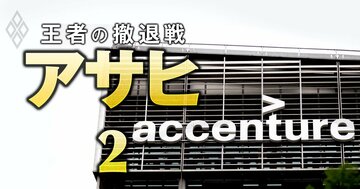Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
ダイニーが6月に実施した大規模な退職勧奨。その実態は、対象者に異例の短期間で退職合意を強要し、拒否すれば「追い出し部屋」へ異動させる違法性の高いプロセスだったことを第1回で明らかにした。では、退職勧奨を受けた元社員が実際に裁判に踏み切るとどうなるのか。長期連載『スタートアップ最前線』内の特集『ダイニー“AIリストラ”の虚構』第2回の本稿では、退職合意書にサインした元社員が訴訟で主張すべき違法性のポイント、裁判の勝率、勝訴時に得られる損害賠償の具体的な金額について、スタートアップ企業の労務問題に詳しい後藤亜由夢弁護士に聞いた。適法な手続で人員整理を進めたいスタートアップ経営者も必見だ。(聞き手/ダイヤモンド編集部 永吉泰貴)
資金難のスタートアップ事情を考慮
適法に社員を辞めさせる現実的な方法は?
――スタートアップ企業から「社員を辞めさせたい」と相談を受けた場合、どのように助言しますか。
まず前提として、弁護士は大きく労働者側と使用者(会社)側を担当する弁護士に分かれています。会社側を担当する弁護士は、不文律として労働者側の案件を扱わないのが通例です。私たち東京スタートアップ法律事務所は、労務案件に関しては基本的に会社側、とりわけスタートアップ企業を中心に手掛けています。
その上で、スタートアップ企業から「辞めさせたい社員がいる」と相談を受けた場合、助言する方向性は二つのパターンがあります。
一つ目は、遅刻や業務命令違反など、就業規則に違反している社員を辞めさせたいケースです。この場合、違反の内容にもよりますが、明確な違法行為の場合などを除き、まずは注意指導や最も軽い懲戒処分としての戒告処分を行い、改善が見られなければ懲戒処分を段階的に重くしていきます。その過程で、任意の退職を促す方向での退職勧奨を実施していくと、当該社員は自ら退職を選ぶことも多いです。
二つ目は、社員に就業規則違反はないものの、業績悪化や社員のスキル不足など、経営上の事情から辞めさせたいケースです。この場合、社員本人に法律上の非はないため、会社の状況を丁寧に説明し、退職金の条件も含めて説得を重ねていくことが多いです。
――社員が就業規則に違反している場合でも、解雇はできませんか。
例外として、窃盗や暴行などの犯罪行為レベルの重大な違反行為であれば、即時解雇も可能となる場合があります。しかし遅刻や無断欠勤、通常の業務命令違反といった程度では、原則として即時解雇はできません。まずは戒告など軽い処分から始め、処分を重ねつつ、その上で任意の退職を促すための退職勧奨で対応する必要があります。
――業績悪化など経営上の事情から社員に退職を促す場合、スタートアップの経営者はどのように退職勧奨を進めるのが望ましいでしょうか。
違法な差別的取扱いにならない範囲で、社員一人一人の状況や性格に応じて条件を調整することをお勧めします。
例えば、職場に居づらさを感じ自主的に退職を検討しそうな社員には、あえて退職金を上積みせずに打診することも選択肢の一つです。
一方、強い意志で残留を希望する社員に対しては、退職金を増額するなど条件を変えて合意形成を図ります。具体的には「基本給の2カ月分を上乗せする」といった条件を提示し、応諾を引き出すといった手順です。
――大手企業のように希望退職制度で手厚い割増退職金を提示するのは、スタートアップでは難しいのでしょうか。
多くのスタートアップは資金的な余裕が乏しく、大規模な希望退職制度を導入するのは現実的ではありません。むしろ資金難に直面しているからこそ、人員削減に踏み切らざるを得ないケースが大半です。
スタートアップの場合、大手企業のような「基本給6カ月分の退職割増金支給」といった手厚いプログラムが難しい場合も多いため、社員一人一人の状況や性格に応じて、違法な差別的取扱いにならない範囲で個別に退職勧奨の条件を設計するよう助言しているのが実情です。
――ここからはダイニーで実施された退職勧奨について、実際の退職合意書や複数の対象者の証言を基に詳細をお伝えします。その上で、適法か違法かについての法的な評価を伺います。
ダイニーの退職勧奨について法的な評価を聞くと、後藤弁護士は手続面で違法性の高い点を指摘した。その上で、元社員が裁判を起こした場合に主張すべきポイントや訴訟の勝率、さらに想定される損害賠償額についても次ページで解説してもらった。