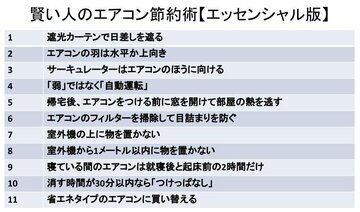ねるねるねるね味とソーダ味が定番商品(著者撮影、以下同)
ねるねるねるね味とソーダ味が定番商品(著者撮影、以下同)
『ねるねるねるね』は、粉と水を混ぜると、色が変わってふくらむ「ちょっとおもしろいお菓子」として、大人から子どもまで認知されている。来年で発売40周年を迎えるが、少子化の今もスーパーで生き残り、「知育菓子」と名乗り仲間も増えて、存在感がさらに増している。『ねるねるねるね』と知育菓子の現在を、クラシエのマーケティング室菓子部長である菊池光倫氏に聞いた。(フリーライター 大北栄人)
どうやって子どものうちに食べてもらえるか
――少子化ですけど、ねるねるねるねはずっとありますね。
今3~12歳の人口が大体1000万人と言われてる中、『ねるねるねるね』を始めとした知育菓子のユーザーは年間600万人。そのうち9割がお子さんなんです。母数が1000万人ありますから、少子化が問題になってくるのはまだ先だと考えてます。
ねるねるねるねは、来年40周年です。1986年発売当時の子どもたちが親世代になってお子さんと一緒にやったり、20代30代の大人、特に女性が懐かしさから飲み会などで友達と一緒にやるという話は聞いたりします。知育菓子はコミュニケーションのツールや人間関係の「触媒」のような一面もあるんですよね。
――お菓子というには変わったものですよね。
大人になって突然ねるねるねるねを食べ始める方は少ないですよね。大人で買われる方は、子どもの頃にすごく好きだったり逆に買ってもらえなかったり、なんらかの体験があることが必要なんです。そのためにはとにかくお子さんに買っていただくことにいろんなリソースを投入してます。
今は(クラシエから販売する知育菓子の)種類もどんどん増えて現在で23種、地域限定も合わせると27種類も出ています。スーパーの店頭で上から下まで並べて手にとって体験していただくのが重要。
 スーパーのお菓子売り場には知育菓子の棚が出来上がることも
スーパーのお菓子売り場には知育菓子の棚が出来上がることも