高額療養費の世帯合算は
申請しないと受けられない
高額療養費は、患者が1カ月に支払う医療費の自己負担部分に上限を設けることで、医療費が過度な負担にならないように配慮した制度だ。医療費が一定額までは通常通りに1~3割を支払うが、所得に応じて決められている限度額を超えた部分の医療費については、患者負担が軽減されるという仕組みになっている。
25年10月現在、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額は、下図のように所得に応じて5段階に分類されている
例えば、(ウ)の年収約370万~約770万円の人の1カ月当たりの上限額は、【8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%】。医療費が26万7000円までは、その3割の8万100円を支払うが、この限度額を超えた部分の医療費の自己負担割合は1%になる。仮に医療費が100万円だった場合、最終的な自己負担分は8万7430円だ。
この制度があるおかげで、医療費そのものが高額になっても、患者の負担は一定範囲内に抑えることができる。
以前はいったん医療費の3割を支払った後で、加入している健康保険組合に患者が申請して、高額療養費の上限額との差額を還付してもらう手続きが必要だった。だが、患者の所得区分を証明する「限度額適用認定証」が作られたことで、還付手続きの手間が省けるようになった。
さらに、現在はマイナ保険証で受け付けをして、高額療養費の「限度額情報の提示」に同意すれば、認定証の提示も必要ない。
このように、高額療養費は自動的に利用できるようになってきているが、中には自分で手続きしないと取り戻せないお金もある。それが「世帯合算」で、「複数の医療機関を受診している」「同じ月に家族の医療費も高額になった」という場合は、患者自らが申請してお金を取り戻す必要がある(ただし、75歳以上の後期高齢者医療制度では原則的に手続き不要)。

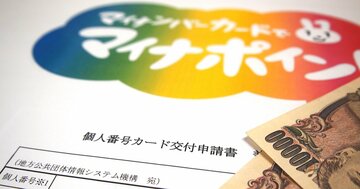

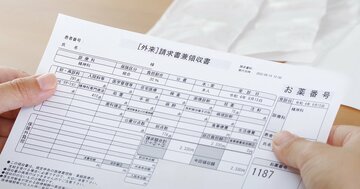
![医療費控除で「知らないと大損」5大ポイント、国税庁申告サイトの“罠”は健在[2023年上期ベスト3]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/7/360wm/img_278ac715f8c5463446993af7d8679634130327.jpg)



