申請の期限はどのくらい?
院外処方も薬代も忘れずに
このように、同一世帯の家族の医療費でも、世帯合算の対象にならないものもあるので、注意が必要だ。高齢の親と同居しているケースでは、親が74歳未満で被扶養者として子どもの公的医療保険に加入していれば世帯合算できるが、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合は合算対象にはならない。
といはいえ、対象になる場合はきちんと申請することで医療費の負担は軽減できる。①のA子さん夫婦のケースで、負担軽減額を確認してみよう。
A子さん夫婦の公的医療保険適用前の医療費は、それぞれ25万円ずつ。窓口では3割の7万5000円ずつ自己負担し、夫婦合計で15万円を支払っている。だが、世帯合算するとA子さん夫婦の高額療養費の自己負担限度額は、【8万100円+(医療費の合計50万円-26万7000円)×1%=8万2430円】になる。そのため、健康保険組合に申請すると、窓口で支払った15万円との差額の6万7570円を取り戻すことができるのだ。
このように世帯合算を利用すれば、医療費の負担をさらに軽減できる可能性があるが、制度があることを知らずに損している人もいるのではないだろうか。
とくに忘れがちなのは、院外処方の薬代だ。その病気やケガの治療のために薬局で支払った薬代は、金額に関係なく病院に支払った医療費とまとめて高額療養費の計算ができる。また、70歳以上の人は「2万1000円以上」という縛りがなく、金額に関係なく支払った医療費の自己負担分を全額合算できるので、忘れずに計上したい。
公的医療保険の給付金の時効は2年間で、診療月の翌月1日から2年以内に申請しないと、給付を受けられなくなってしまう。最近、家族が同時に病気やケガをして医療費が高額になったことがあるという人は、申請漏れがないかどうか確認してみよう。
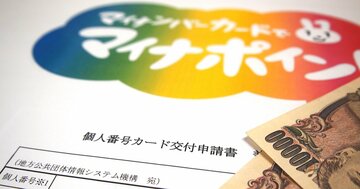

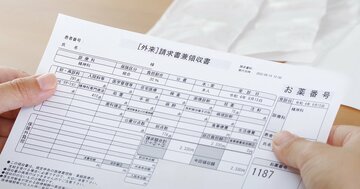
![医療費控除で「知らないと大損」5大ポイント、国税庁申告サイトの“罠”は健在[2023年上期ベスト3]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/7/360wm/img_278ac715f8c5463446993af7d8679634130327.jpg)



