違う公的医療保険に加入していたら
同一世帯でも合算できない
高額療養費は、歴月単位(その月の1日~末日)、個人単位、医療機関単位で、かかった医療費に対する自己負担額を計算することになっている。また、医療機関ごとの医療費は、次のようなルールがある。
・同じ医療機関でも、医科と歯科は別々に計算する
・同じ医療機関でも、通院と入院は別々に計算する
・通院による治療で、病院や診療所に支払った医療費と、薬局に支払った医療費はまとめて計算する
このように、かかった医療費は個人ごとに計算するのが原則だが、同一世帯で暮らす家族の医療費は合算して高額療養費を申請できる。ただし、家族の医療費ならなんでも申請できるわけではなく、そこには一定のルールがある。世帯合算ができるのは、次の要件を満たした場合だ。
・同一世帯の家族の医療費であること
・同じ月に使った医療費であること
・同じ公的医療保険に加入していること
・70歳未満の人は自己負担額2万1000円以上になった場合(70歳以上の人は金額にかかわらず全ての自己負担額が合算対象)
では、どのようなケースが世帯合算の対象になるのか、70歳未満の人の場合で具体的に考えてみよう(※窓口負担割合は3割、高額療養費の所得区分は、前ページの図(ウ)の年収約370万~約770万円の場合)。
【世帯合算の対象になる?ならない?】
① 専業主婦のA子さんは、被扶養者として夫の会社の健康保険に加入しているが、旅先で夫婦同時に交通事故に遭い、医療費の自己負担額がそれぞれ7万5000円ずつかかった。
→〇 同じ公的医療保険に加入し、同時に2万1000円以上の医療費を自己負担しているので合算対象
② 心臓疾患で病院に入院し、高額療養費適用後の自己負担額が11万円だったB男さんは、運悪く同じ月に骨折して別の診療所で通院費用3万円を自己負担した。
→〇 1人でも複数の医療機関を受診して、2万1000円以上の自己負担をしていれば合算対象
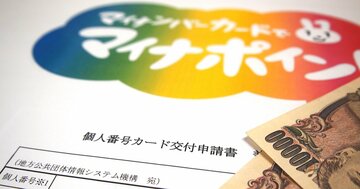

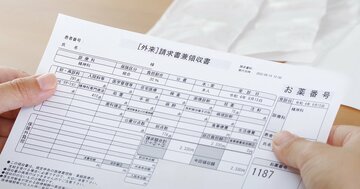
![医療費控除で「知らないと大損」5大ポイント、国税庁申告サイトの“罠”は健在[2023年上期ベスト3]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/7/360wm/img_278ac715f8c5463446993af7d8679634130327.jpg)



