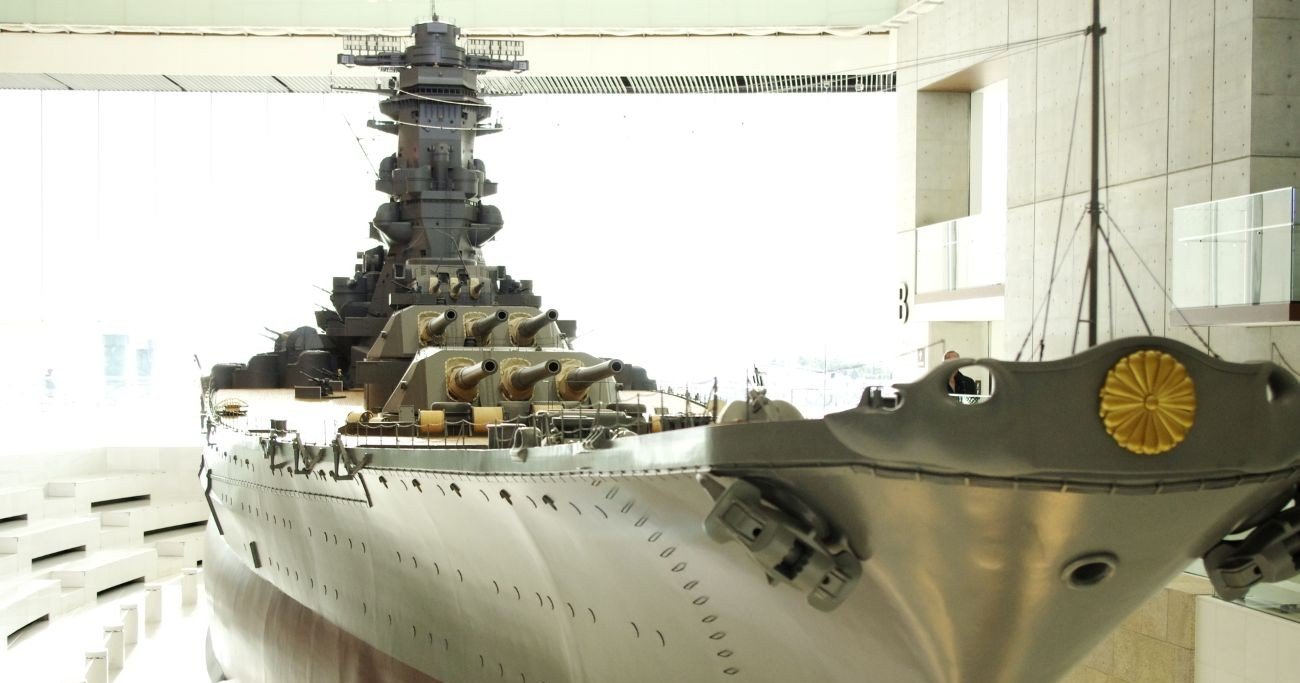 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
初めてB-29に「特攻」した日本の戦闘機「屠龍」。その後部搭乗員・梅田春雄と、『銀河鉄道999』『宇宙戦艦ヤマト』『戦場まんがシリーズ』などで知られる漫画家・松本零士には、意外な絆があった。梅田の証言から、戦場と創作をつないだ知られざる物語をひも解く。※本稿は、戸津井康之『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
米爆撃機B-29を迎撃できた
数少ない万能機「屠龍」
「米のP-38『ライトニング』や独の『メッサーシュミットBf110』のような双発(編集部注/2つのエンジン)の万能戦闘機を直ちに開発せよ」
こんな陸軍からの高い要求を受けた戦闘機の設計者は川崎航空機(現川崎重工)のエース、土井武夫。
ゼロ戦の設計者である三菱重工のエース、堀越二郎とは東京帝国大学工学部航空学科でともに学んだ同期生だ。堀越は「ゼロ戦」や「雷電」など数々の海軍機の傑作機を設計したが、片や土井は、「屠龍」や「飛燕」など陸軍の歴代名機の設計を数多く手掛けたことで知られる。
なぜ、「屠龍」は万能機と呼ばれていたのか?
梅田(編集部注/梅田春雄。陸軍二式複座戦闘機「屠龍」後部搭乗員)が分かりやすく、こう説明してくれた。
「まず、単発、単座機と比べて後部座席を備え、機体が大きいですから、重武装の搭載が可能で、また、武装と同時に多種多様な機器を余裕で積み込める搭載能力がありました。
つまり、出撃する用途に応じて、使う装備をいろいろと選ぶことができたのです。たとえば、機関銃、機関砲の代わりにカメラを積めば偵察機となり、爆弾を積めば爆撃機にもなり、高性能の航法装置や通信機を搭載すれば、編隊の指揮機にもなるのです」







