大規模開発が順調に進むかが
「大胆な数値目標」達成のカギ
生活ソリューション部門では、新たな事業の柱と位置付ける不動産・ホテル事業が、前述の通り、増収減益となった。高輪ゲートウェイシティ開業によるオフィス賃貸収入やホテルなどの売上増が増収に寄与した一方、不動産販売の減収減益、施設新規開業による費用増の影響で前年比17.0%の減益となった。
不動産販売とは一般的にイメージされる住宅などの分譲ではなく、社有地や取得した用地を開発し、その一部をJR東日本グループが関与する不動産ファンドに売却。その利益を新たな投資に振り向ける不動産の回転型ビジネスだ。
現状は既存物件の売却がひと通りすすみ、次なる開発に向けた“種まき”の段階だ。2027年度までに1000億円規模の投資という数値目標を達成し、「回転」が軌道に乗れば大きな利益が期待できる。
また、今年度末には高輪ゲートウェイの全面開業、大井町トラックスの開業が控えている。両施設ともオフィス、テナントのリーシングは順調とのことで、今後は大きな収益源となることが期待される。むしろ問題は、工費の増大や人手不足により工事が停滞または事業そのものを見直す動きが、都内各地で相次いでいることだ。
同社は2031年度の営業収益を、2025年度業績予想から1兆円積み増して4兆円増とする大胆な数値目標を掲げているが、エンジンとなるのが不動産セグメントだ。今後の大規模開発が順調に進むかが、目標達成のカギとなってくるだろう。
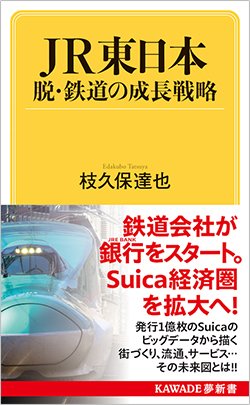 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
冒頭に「物足りない数字」と書いたが、事業環境は好転している。今回の決算では4月に発表した通期業績予想を上方修正するとともに、中間配当・期末配当を増額すると発表した。
営業収益は期首予想比350億円増の3兆580億円、営業利益は同180億円増の4050億円の増収増益としている。中でも運輸は営業収益が同300億円増、営業利益が同150億円増となり、増収増益のほとんどを占めている。
これを2024年度と比較すると営業収益は全体で5.9%増、うち運輸は4.4%増、不動産・ホテルは13.6%増、営業利益は全体で7.5%増、うち運輸は9.0%増、不動産・ホテルは3.0%増となり、中間決算とは印象が全く変わってくる。
JR東日本は曲がり角を迎える鉄道業界でも、特に変化の渦中にある鉄道事業者だ。目先の数字で業績を判断するのではなく、中長期的視点で見極める必要がある。
ワンマン・ドライバレス運転の拡大や、前述のチケットレス化など鉄道のオペレーションコスト削減は予定通り進むのか。これは技術開発の面だけでなく、法制度や社会受容の問題も絡むだけに一筋縄では行かない。新線建設や不動産開発の遅延リスクもある。2030年代を見据えた高い目標に本当に到達するのか、各施策の進捗度に注目しながら追っていきたい。







