次の論点は受益の算定方法だ。貸付料は需要予測をもとに開業前に決定するため、どうしても実績との乖離が発生する。北海道新幹線新青森~新函館北斗間を除き、いずれの線区も実績が上振れており、JRが貸付料以上の受益を得ているのが実情だ。
財務省は需要予測と実績値の乖離を、北陸新幹線高崎~長野間が2割増、長野~上越妙高が5割増、上越妙高~金沢間が6割増、計176億円分と試算。また、北陸新幹線の延伸に伴う高崎~長野間の増収効果(接続利益)を貸付料に反映すべきと主張する。
だが、それが需要予測の不備によるものか、JRの経営努力の結果なのか判別は難しい。現行制度では需要予測を上回る収入はインセンティブとして、JRの利益とすることが認められている。公共事業で金儲けはさせるわけにはいかないといいつつ、全く利益にならないのならJRは営業を引き受けないだろう。国交省もあえて一定の利益が出る貸付料設定としている節がある。
しかし、問題の本質は検証困難な需要予測をもとに30年の長期固定契約を設定するリスクだ。JR東日本は来年春、民営化以来初となる運賃改定を実施する。運賃を値上げすれば受益も増えるが、貸付料には反映されない。前述のように貸付料は既に建設された路線ではなく、次の工事費に充てられるものなので、極端な話、30年で貨幣価値が半分になったらスキームは破綻してしまう。
高速道路会社が債務返済機構に支払う貸付料は、交通量推計をふまえて定期的(1~5年程度)に見直しており、整備新幹線も定期的に実態に即した改定をすべきとの主張には一理ある。
そして3つ目の論点が、JR東日本の喜勢陽一社長が11月11日の定例社長会見で言及した、政府との「契約」の存在だ。喜勢氏は30年経過後の貸付料について「施設の状況に応じた通常の維持管理費用とする」ことを「公文書によって行政契約として結んでいる」と述べた。
その上で「建設費が足りないからといって貸付料期間を延長することには、単純にはならないんじゃないかなと我々は考えています」として、ルールの変更にはJRの合意が必要との認識を示した。ここまで見てきたように、大規模改修の費用を織り込んだ減額改定はあっても、算出根拠を変更した一方的な増額改定は認めないとの立場だ。
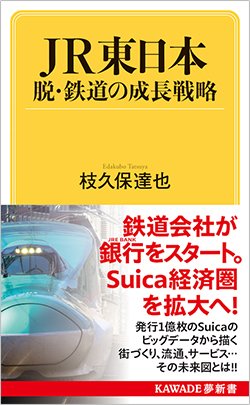 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
「契約」についてJR東日本に尋ねたところ、会見の発言が全てとして詳細は明らかにしなかった。契約内容と主張は今後のヒアリングで出てくると思われる。
他にも論点はあるが、ひとまずここで区切りたい。これらを概観して思うのは、議論が始まったばかりという点を差し引いても、貸付料収入という「入口」の議論に終始していることだ。
喜勢社長が「建設費が足りないからといって」と述べるように、議論の前提は多額の費用を要すると見込まれる敦賀~新大阪間の建設財源であり、これを確保したい国交省と、国庫負担を削減したい財務省の思惑が交錯する。整備新幹線の主要区間が「30年」を迎えるのは2040年代であり、改定がすぐに貸付料の増収につながるわけではないが、現在も行われているように将来の貸付料収入を担保に借り入れして、工事費に充てたい考えなのだろう。
今さら整備新幹線プロジェクトは止められないので、現行計画は完遂するのだろう。ではその先はどうするのか。新たな「整備計画」を策定して建設を続行するのか、それとも既設線の維持管理に回すのか、あるいは鉄道政策の財源として活用するのか。行政の予算が肥大化するのは、一度手にした財源を既得権として、新たな使い道を探すからだ。貸付料の「出口」が明確にならなければ、JRは「入口」に同意しないだろう。議論の行方を注視したい。







