また社員同士で、「プロの仕事人」とはどのような存在であるべきか、議論が交わされているそうである。ロート製薬が他社に先駆けて複業・副業を解禁したことも、こうした同社の姿勢の延長線上にある(注5)。
ライオンは自社の社員の副業を解禁しているだけでなく、副業の受け入れも行っている。つまり、「送り出し(副業申告制)」と「受入れ(副業公募制)」の両軸が存在する。
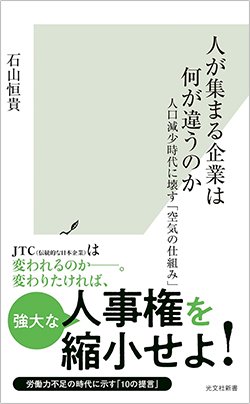 『人が集まる企業は何が違うのか 人口減少時代に壊す「空気の仕組み」』(石山恒貴、光文社)
『人が集まる企業は何が違うのか 人口減少時代に壊す「空気の仕組み」』(石山恒貴、光文社)
ライオンはこの取り組みの目的を、「企業と人は対等」であることを前提に、「人に選ばれる企業」を目指すためだとしている(注6)。
3社は社員を自律した個とみなし、多様な働き手を包摂していることで共通している。その場合、結果的に副業を推奨することにもつながっている。
対照的に、先述の日本企業的パターナリズムの典型例として紹介した経営者は、副業を否定的に捉えていた。
副業の送り出しと受け入れは社外の知を社内に取り入れることでも有効であろう。その意味では、個人の観点のみならず、企業の観点でも生産性向上に寄与するであろう。副業に対する企業の姿勢は、日本企業的パターナリズムの存在の有無を判断するリトマス試験紙になるとも考えられる。
(注5)高倉千春(2023)『人事変革ストーリー:個と組織「共進化」の時代』光文社
(注6)人事ポータルサイト【HRpro】「ライオンが副業を推進する意義とは―『副業によって人材開発を促進する』という人事の挑戦」







