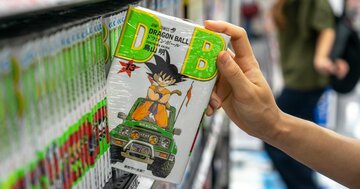例えば、サービスが始動した11月1日の生配信で松本人志からは「ちょっと地上波、テレビが窮屈になってしまっている」「“地上波病”っていうとあれですけど、ちょっと自分の中でも『こんなん言っていいのかな』っていうのはあるけど、基本的にこっちには(規制は)ないので」など、地上波についての言及があった。
この“テレビのような”ダウンタウンプラスを通して感じたのは、予算でも過激さでもない地上波の限界だった。
まずは実験性だ。1日の生配信のオープニング映像には「感謝」「挑戦」などの言葉とともに「実験」という言葉があった。実際、ダウンタウンプラスは松本の壮大な実験場のような印象を受ける。
中でも松本人志が「笑い」を様々な角度から実験・検証するというコンテンツ「松本教授の笑いの証明」での、笑い飯の登場回は面白かった。「笑い飯の漫才は何回目が一番面白いか」を検証すべく、彼らに同じネタの漫才を6回も行わせるのだが、3回、4回と同じネタを繰り返すことで、初見とは違う面白さが出てくる。同じネタをほぼ寸分違わず繰り返すことのできる笑い飯の技量にも唸らされた。
平成の深夜番組のような印象も感じたが、同時に「これは地上波では絶対に無理だ」と確信させられた。 視聴率やザッピング対策に追われる地上波では、同じネタを6回も繰り返すような番組の作り方は許されないだろう。視聴者が離脱しないよう、常に新しい刺激を与え続けなければならないからだ。しかし、ここではそれが許される。この「無駄の贅沢」こそが、かつてのテレビのバラエティ番組が持っていた豊かさだったと思い返した。
次に自主規制だ。あえて過激さを売りにはしないが、規制は地上波よりも緩い。今よりも少し緩いラインは、こちらも平成までのテレビのような印象を受けた。
片方が海外にルーツを持っているコンビが自国の文化・習慣を自虐するネタを披露する「漫才インターナショナル」では、地上波でやれば「その国をバカにしすぎている」とSNSで炎上する可能性もあるかもしれないネタが披露された。ただ、無法地帯ではない。漫才の中で本当に危険な場所にはいわゆる「P音」が入り、事前には次の注意文が流れた。