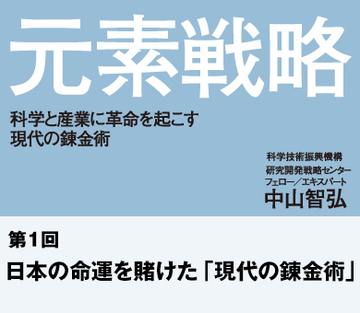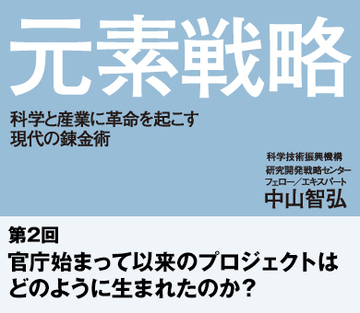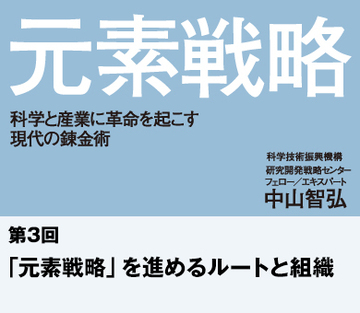日本を支える「2つの化学科」
──北川先生は「元素戦略」にどのようなスタンスで関わられてきたのでしょうか?
 北川宏(きたがわ・ひろし)
北川宏(きたがわ・ひろし)京都大学教授・博士(理学)。昭和36年12月5日生まれ。1991年3月京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。1991年4月岡崎国立共同研究機構(現自然科学研究機構)分子科学研究所に着任、助手として分子素子研究に従事。1992年3月「ペロブスカイト型混合原子価錯体の研究」にて博士(理学)京都大学、1993年英国王立研究所客員研究員、1994年4月北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科助手、2000年1月筑波大学化学系助教授、2003年5月九州大学大学院理学研究院教授。2005年から2012年まで科学技術振興機構科学技術振興調整費研究領域主幹、2005年から2008年まで九州大学総長特別補佐(構造改革担当)、2009年4月京都大学大学院理学研究科教授に就任、2013年第5回化学サミット議長(テーマは元素有効利用)。現在、文部科学省研究振興局科学官、南京大学併任教授。4月から京都大学理事補(研究担当)。日本化学会学術賞、井上学術賞、マルコ・ポーロイタリア科学賞などを受賞。原著論文200報余。
北川 私自身は「元素戦略=化学」というスタンスです。幸いなことに、現在、日本の化学産業は非常に活発ですが、化学というのはサイエンスと産業とが直結している面があって、たとえば、プラスチックや電気製品の中の部品、半導体をつくるにも化学の成果を使っています。化学産業がダメになると、その国全体の産業がダメになると言ってよいと思います。
一番典型的な例はイギリスです。イギリスにはICI(Imperial Chemical Industries)という世界的な化学メーカーがありましたが、2008年にオランダの化学メーカーの傘下に入りました。業績が悪くなった理由の1つは、イギリスの場合はサイエンスを重視し、エンジニアリングを軽視しすぎる傾向があったことです。
ところが、日本はちょっと特殊で、大学には理学部系の化学科と、工学部系の応用化学科がありますね。なぜ2つの化学科があるかというと、理学部系はもともと旧文部省(現文部科学省)が、工学部系は旧工部省(現経済産業省)がつくったという経緯があるからです。もちろん、最終的には現在の文部科学省が大学を管轄することで統合されましたが、「2つの化学科」が存在することは世界的にも珍しいことです。おかげで、理学部系ではベーシックな基礎化学・純粋化学をやり、工学部系ではエンジニアリングを担当するという、非常にうまい棲み分けが伝統的にできています。エンジニアリングというのは、化学工学とかプラントづくり、コンビナートなどの実用に役立つ化学のことです。
これに対して、イギリスでは理学部的な基礎化学を重視しすぎました。たしかに18世紀の産業革命の時代には、基礎化学でも十分に産業に対応できたといえますが、現在の産業はハイエンドになっていますから、基礎化学とエンジニアリングとを一足飛びに結びつけるのは難しい話です。日本の場合は両方のバランスが取れているので、基礎化学が伸びれば企業のエンジニアリングも伸びる、企業のエンジニアリングが伸びれば大学の基礎化学も伸びるという好循環体制をもっています。
日本には数多くの化学メーカーがあって活発に活動しています。その活動の根幹になっているのはまさしく「化学」であって、「元素戦略=化学」という僕の立場から言えば、「元素戦略」を軽視すると、化学が部品・材料をすべてつくっていますから、日本の産業はいっぺんにダメになってしまいます。
──北川先生は「代替という言葉は嫌いだ」とよく発言されているようですが、それはどのような意味なのでしょうか?
北川 いや、「代替」はもちろん重要だと思っていますよ(笑)。「代替」には2つの意味があって、希少元素を一般的な元素に代える代替と、有害元素を他の安全な元素に代える代替ですね。「元素戦略」でも「代替」は重視されています。
ただ、私自身はもともと、理学部で育ち、理学部で長く教育・研究を行ってきているので、どちらかというと、「0を1にする」ほうが好きで、私の関心はそちらにあるということです。たしかに、いまここにある機能をそのままにして値段を安くするとか、他の元素に置き換えるといったことは社会的に重要な貢献です。けれども、大学の研究者というのは企業の研究者が手を染めにくいような研究をするのが本来の役目です。1を2にしたり、3を5や10にしたりするのは企業でも可能だと思いますが、われわれは「0を1にする」仕事をすべきなのです。そういう意味で「代替」という発想に捕らわれるのは好きではない、という考え方ですね。
出口戦略を意識するようになった研究者
中山 「元素戦略」ではサイエンスで終わるのではなく、その研究でどんな製品ができるのかといった「研究成果の出口」まで考えて研究をすることが重要視されています。それが従来のアカデミックにおける研究姿勢と違う点だと思いますが、「そんなのは企業の考えることで、本末転倒だ」という大学の先生も多いですね。北川先生は出口戦略についてはどう評価されていますか?
北川 重要なのはよくわかっています。私は京都大学の理学部という、ちょっと世間とは隔絶した世界に長く棲んでいました。京大理学部というところは、学問的に非常に純粋・ピュアで、神聖なサイエンスの場に身を置いているというイメージで研究をするところでした。何らかの目的をもって研究することさえ、「やましいことだ!」と罵られるような場所でした。私はそんな場所でずっと育ち、38歳まで助手をやっていましたから、当時は非常にピュアで、「企業と共同研究するなんてとんでもない、心が穢れる!」と本気で思っていたくらいです(笑)。
ところが、筑波大学に移って助教授になった時に、ひょんなことからある企業と共同研究することになったのです。最初は嫌でしかたなかったのですが、実際に企業の研究者と付き合ってみると、非常に優秀です。驚きました。しかも私が考えもしないアイデアを次々に出してくれる。企業からのフィードバックの多さにも驚きました。心底、周りを見る目が変わりましたね。
中山 同じ大学の先生とか、大学間の共同研究ではどうですか?
北川 大学間の共同研究は難しいですね。そもそも同じ分野の人であればライバルであって、最初からうまくいきません。それが企業の場合、こちらはいい論文を書きたいし、企業側はいい商品をつくりたいということで共存共栄できます。アイデアを出し合ったほうがお互いにトクです。畑の違うプロフェッショナルと付き合うと、毎回、新しい発見がありますし、基礎研究にも弾みがつきます。そういう意味で、自分の研究を製品開発に結びつけて考える、つまり「出口を考える」ということは大学の研究者にとっても、非常に重要だと思うんです。自分の研究に跳ね返ってきますから。
中山 ただ最近は「出口、出口」と言い過ぎかな、と思いますね。出口は大切であっても、研究者すべてが出口ばかりに意識を向けてしまったら、次の世代は育たないですからね。
北川 そうなんです。僕らが自然に企業の人と共同研究していくのはいいけれど、最近は国が「出口戦略が大切だ」と言い過ぎます。出口が重要なことは僕も十分に承知しています。そもそも、国立大学の場合は税金を使って研究をやっているわけですから、その研究成果が社会にまったく役に立たないものだったら研究をしても意味がないことです。ただ、国がそれを強制しようという風潮は心配です。