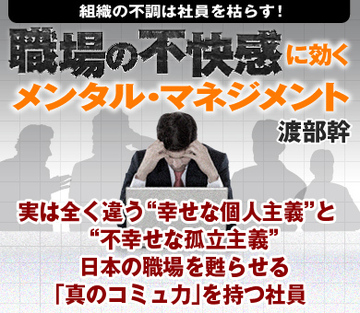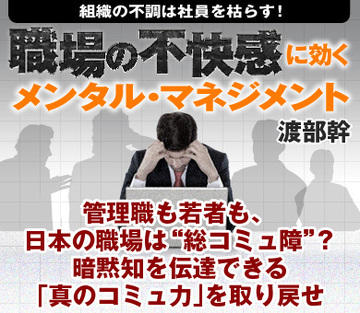日本人なのに日本人をこき下ろす
女性運動家のプロパガンダの違和感
本連載「黒い心理学」では、ビジネスパーソンを蝕む「心のダークサイド」がいかにブラックな職場をつくり上げていくか、心理学の研究をベースに解説している。
最近、グローバル人材の開発、グローバルコミュニケーションの技術といった話題がよく聞かれる。
先日、日本であるビジネスコンサルティング会社のセミナーに参加させていただいたが、いかにして多様性のある人材をマネジメントするかという主題の中で、グローバル人材の重要性が議論されていた。
筆者も対談形式の発表をさせていただいたのだが、その発表準備や打ち合わせの中で気づいたことがあった。グローバルコミュニケーションの本質とは何かという問題だ。それに気づいたのは、筆者がまだアメリカにいた頃の出来事を思い出したからだ。
当時筆者は、ロサンゼルスのある大学の大学院生として、博士号取得を目指して勉強していた。留学生に限らず、米国の大学院生は「貧乏」と相場が決まっていて、筆者もお金のかかる旅行や日本への帰省などめったにできず、大学と家の往復だけの毎日だった。
筆者のいた大学はマンモス校だったので、筆者以外にも日本人の留学生はたくさんいた。だが筆者の専攻にはあまり日本人が多くなく、友人たちも大抵アメリカ人か欧州からの留学生だった。
それでも、日本人の多いロサンゼルスに住んでいると、日本人と知り合いになる機会はそこそこ訪れる。たまたま筆者の学部を訪問してきた、学外の日本人女性研究者が筆者を見つけ、声をかけてきたことがあった。
当時で30歳くらいのその女性は、もう10年くらいアメリカ暮らしをしていて、社会学専攻のポストドクトラル研究生(博士号取得後の「研究員」)だった。彼女の専門は、フェミニズムを含む社会活動だった。学者というよりも運動家に近く、彼女は私に「米国大手企業が、東南アジアの子どもたちを労働搾取している」ということを訴えたビラを渡してきた。筆者の所属学部の学生たちに訴えて、この運動を支持してほしい、と要請してきた。