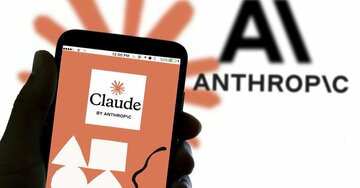2008年9月15日。今から思えば、この日が世界経済の「転機」になった。この日、米国の誇る大手投資銀行であるリーマン・ブラザーズは、連邦破産法11条を申請し、破綻した。
その日を境にして、世界経済は坂を転げ落ちるように下落の一途をたどり始めた。おそらく、後世の歴史家は、この日を「金融資本主義の運命の1日」と位置づけることだろう。リーマン・ブラザーズの破綻は、世界経済にとってそれほど重要な出来事だったのである。
リーマンが破綻したことで、金融市場、特に金融機関同士の資金貸借市場は、事実上機能不全に陥った。金融市場では、「相手が破綻して貸した資金が戻って来ない」と思えば、誰も資金を貸し出す者はいない。
当たり前のことなのだが、米国政府がリーマンを救済せずに破綻を容認したことで、多くの市場参加者一瞬にして凍てついたことだろう。「暗黙の了解」が裏切られたからだ。
このような事態に陥るまでの経緯を、詳しく振り返ってみよう。それまで、市場参加者のなかには「政府は最終的に大手金融機関を救うだろう」という“甘え”があった。だからこそ参加者は、取引相手に資金を貸し出すことができたのだ。
昨年3月、事実上破綻したベアー・スターンズのケースでは、米国政府は多額の救済金をつけてJPモルガンに救済合併させた。誰もが「リーマンもそうなるだろう」と予測した。
しかし、リーマンの件では様子が違った。ポールソン財務長官は、記者会見で「リーマンを救うつもりはない」と明言した。この一言が、金融市場の楽観的な見方を一変させたのだ。
そのため、金融市場には「政府は大手金融機関が破綻の危機に瀕しても、見殺しにするかもしれない」との“コンセンサス”ができ上がり、金融機関は一斉に「専守防衛型ムード」に入った。市場では途端に取引が細り始め、金融機関のなかには、資金繰りが悪化するところも目立ち始めた。
そうなると、金融機関が「企業や個人に対する信用を絞る」のは当然である。その結果、必要なところに資金が回らなくなり、経済活動が低下する。特に、借金をして消費を増やしてきた米国の家計にとって、「おカネが借りられなくなる」という状況は決定的だった。
米国のGDPの約7割を占める消費から、エネルギーが急速に薄れていった。消費が盛り上らなければ、米国経済は成長のエンジンを失う。米国の景気が急減速すると、わが国や中国を始め、世界経済に深刻なマイナスの影響が及ぶことは避けられない。こうして、世界経済は、未曾有の急降下を余儀なくされたのである。