ダイヤモンド・オンラインplus


健康食品の通販事業を手掛ける、やずやでは、ビジネスの根幹を担う通販システムを刷新した。長年にわたり培ってきた通販のノウハウを全面的に投入し、顧客起点のダイレクトマーケティングをより強力に推進していくのが狙いだ。同社のビジネス戦略や新システムにかけた想い、今後の展望ついて、やずやの代表取締役社長の矢頭徹氏に話を聞いた。

中小企業向け事業保険のエキスパートとしてあり続けるために、エヌエヌ生命は具体的にどのような取り組みを行っているのか。営業活動の黎明期から、現場の第一線で活躍してきた三輪泰久・営業担当執行役員に聞いた。
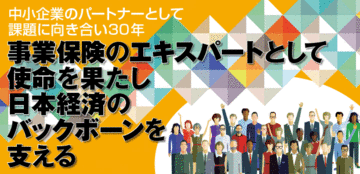
企業向けICTサービス「USEN GATE 02」で豊富な実績を持つUSEN。サービス提供開始から15周年を迎え、導入企業は約4万社に上る。ニーズに応じたマルチサービスをワンストップで提供できることが強みだ。

Looop(ループ)は、太陽光発電システムの開発・販売・管理を手掛けるほか、自社社太陽光発電所の設置、電力小売事業なども行っている。再生可能エネルギーにこだわりながら、社会インフラの構築も含めた幅広いビジネスを創出していく考えだ。次世代のエネルギー社会実現に向け、前例のない挑戦を続けていく。

ハウスメーカー・ヤマヒサのペットケア事業部が2016年10月1日付で独立し、ペット用品専業メーカー「ペティオ」が誕生した。独立の背景にはペットの家族化がある。ペットから家族へ――。オーナーのより高い要望に応えるためにも、迅速な意思決定ができる専業メーカーとなり、飛躍を誓う。

2016年4月に創業30周年を迎えた、オランダにルーツを持つエヌエヌ生命。日本経済の活性化の原動力である中小企業向けの事業保険に特化し、革新的なソリューションと卓越したサービスを提供、この分野では抜きん出た評価を持つ。NNグループの強固なビジネス基盤と「変わりつづける力」を軸に"中小企業のパートナー"としてさらなる飛躍を図る同社の、安定した成長の秘密に迫った。
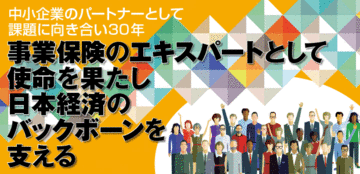
高齢の親から子、孫の三世代へ資産を承継させるために何ができるのか?その答えの一つが「信託銀行の利用」である。相続・贈与に関わる「次世代支援信託」だけでなく、資産運用や住宅ローン、不動産仲介のような現役世代向けのサービスも数多く提供している。

相続・贈与税の負担が大きくなる中、資産をうまく子どもや孫に承継していくには、幾つかポイントがある。多田恭章税理士は、税金面だけでなく、使われ方まで配慮した資産承継が不可欠とアドバイスする。
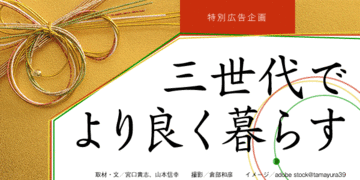
最近ファッションの一つとして、きものを気軽に楽しみたいという男性が増えている。だが着慣れないきものを、どう着こなせばよいのか?男きものの“先達”が指南する。
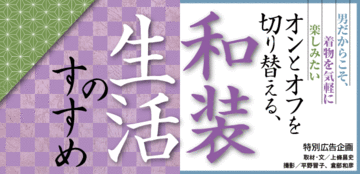
日産自動車のノートが月間の新車販売台数で日産車として30年ぶりに1位を獲得した。好調の要因は電気自動車ノートe-POWERの販売好調である。充電が要らない"新しいカタチの電気自動車”はなにがスゴイくてユーザーに評価されているのか?
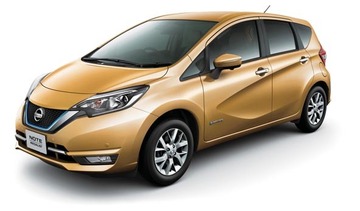
日産ゼロ・エミッションサポートプログラム2(ZESP2)」では毎月2000円で全国5600基以上の急速充電器が使い放題となる。また現在日産リーフを購入するとZESP2が2年間無料となるキャンペーンも実施中だ。

日本初の角膜コンタクトレンズメーカーとして、時代とともに革新的な商品やサービスを次々と送り出してきたメニコン。「1dayタイプ」の新製品を投入した同社は、「レンズの内側に触れない」という独自のこだわりで、コンタクトレンズの新常識を確立しようとしている。

ホンダの純正カスタムカー「ステップワゴン Modulo X」の試乗会が、12月中旬栃木県のツインリンクもてぎで行われた。ミニバンなのにサーキットでの試乗会。しかも参加者は全員家族同伴というユニークな試乗会の狙いと、参加者の声を取材した。

メガFTA(自由貿易協定)をはじめとする自由貿易が世界的に大きな潮流となる中で、企業はどのような対応をしていくべきなのか。さらに、世界各国にまたがるサプライチェーンが複雑性を増す中で、今後のグローバルな物流改革の方向性についても考察を加える。

夕方になると目がしょぼしょぼして、見たいものにピントが合いにくくなる。このような見えにくさをしばしば感じる人には、「スマホ老眼」が疑われる。老眼といえば40代後半から増えてくる症状であるため、“まさか自分はまだ…”と思う人もいるだろう。しかし近年、20代や30代など老眼にはまだ早い世代に、スマホの使い過ぎによる目の不調を訴えるケースが増えているのだ。
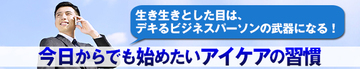
日本人の失明原因第1位となっている緑内障。視神経が障害を受けることで、次第に視野が欠けていく疾患だが、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、自分では気付きにくいという特徴もある。早期発見が重要な鍵となる緑内障について、詳しく見ていきたい。
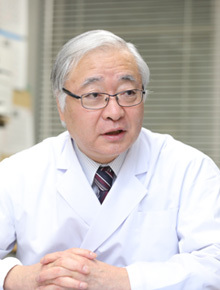
住宅ローン制度について考えていたら、日本人はいつから幸せでなくなったのだろう、という疑問に行き着いた。私は、住宅を買える人には、ぜひ買ってほしいと思っている。だが、このような状況で、住宅を買える人がどれだけいるのだと、暗澹たる気持ちになる。

首都圏で「マンションと戸建ての価格逆転」がささやかれ始めたのは5年ほど前のこと。最初はさほど大きな話題ではなかったが、最近はマンション価格高騰を受け、あえて戸建てを選択する人が増えている。特に子育て世代には、戸建ての価格だけではない魅力も、評価され始めている。
