マツダ
「マツダ(MAZDA)」は、西アジアでの人類文明発祥とともに誕生した神、アフラ・マズダ(Ahura Mazda)に由来している。英知・理性・調和の神アフラ・マズダを東西文明の源泉的シンボルかつ自動車文明の原始的シンボルとして捉え、また、世界平和を希求し自動車産業の光明となることを願って付けられた。また、創業者の松田重次郎の姓にもちなんでいる。
関連ニュース
マツダが「ロータリーエンジン」を11年ぶりに復活、電動化時代の生き残り戦略の鍵は?
桃田健史
マツダは2023年6月、クロスオーバーSUV「MX-30 Rotary-EV」向けにロータリーエンジン量産を復活させた。また、モータースポーツでは欧州で普及が進むバイオ燃料「HVO」の利用を開始し24年に量産化を目指す。マツダのマルチソリューションの行方を各現場から探った。

トヨタが業界騒然人事!次世代EVソフト開発でグーグル出身技術者を見切り、デンソーを頼った裏事情
ダイヤモンド編集部,宮井貴之
トヨタ自動車が、EV(電気自動車)の開発体制を刷新した。EVの競争力の鍵を握るソフトウエアの開発子会社のトップを任せてきた米グーグル出身の技術者を退任させ、後任に、トヨタグループのデンソー幹部を充てたのだ。なぜトヨタは、EVの根幹となるソフトの開発で、デンソーに助けを求めたのか。業界を騒然とさせた人事の裏にある、トヨタの焦燥や、車載OS開発の混乱などを徹底解説する。

#12
「チームトヨタ」は日野自動車斬りで崩壊寸前!次なる脱落者はマツダかSUBARUか?
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
トヨタ傘下の日野自動車と、独ダイムラートラック傘下の三菱ふそうトラック・バスが統合することで、トヨタは日野切りを実施することになりそうだ。豊田章男氏が社長時代に全方位で提携戦略を進めたことで、国内自動車業界における“トヨタ勢力圏”は膨張気味だ。広げ過ぎた「チームトヨタ」にくすぶる三つの火種について解説する。

#10
デンソーがトヨタから独立宣言!?自動車専業から「半導体メーカーへ転身」の仰天プラン判明!
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
世界第2位の自動車部品メーカーのデンソーは、トヨタ自動車への遠慮もあって大型の企業買収を封印してきた。だが、トヨタ依存から脱却するため、民生機器用(非車載用)も含む半導体メーカーに転身する「仰天プラン」があるという。
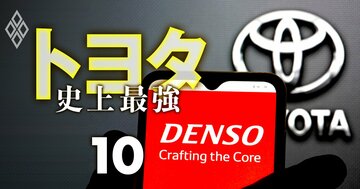
#1
トヨタ御曹司率いるソフト開発子会社“ウーブン”迷走!「社名変更」と「車載OS不調」の真相
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
トヨタ自動車の変革の鍵を握る、気鋭のソフトウエア開発子会社、ウーブン・バイ・トヨタに不穏な気配が漂っている。トヨタの豊田章男会長と、同子会社幹部を務める長男、豊田大輔氏に隙間風が吹いているという。トヨタの未来を左右する電機自動車(EV)などの競争力に影響を及ぼしかねない、車載OS開発などを巡る混乱、そして豊田親子の不和の真相に迫った。

#11
トヨタ、ホンダ、日産…「大変革時代」の生存戦略は?気鋭アナリストが描く5年後の自動車業界ロードマップ
中西孝樹
自動車業界の気鋭アナリストとして知られるナカニシ自動車産業リサーチの中西孝樹代表アナリストが、大変革期に直面する車業界の5年後を大展望。トヨタ自動車をはじめとした日系大手メーカーの生存戦略を分析する。

年収が高い自動車メーカー・部材会社ランキング2022最新版【トップ5】ホンダはトップ3から転落
ダイヤモンド編集部,松本裕樹
上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い自動車メーカー・部材会社ランキング」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は2021年4月期~22年3月期。

年収が高い自動車メーカー・部材会社ランキング2022最新版【74社完全版】意外に低い?SUBARU・マツダの順位は
ダイヤモンド編集部,松本裕樹
上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い自動車メーカー・部材会社ランキング」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は2021年4月期~22年3月期。

マツダCX-60、オール新設計のプレミアムSUVの現在地【試乗記】
CAR and DRIVER
CX-60は、4種のパワーユニットが選べるオール新設計のプレミアムSUV。今回はデリバリーが始まった純エンジンの直6ディーゼルをメインに試乗。PHEVを含め現状の完成度を整理した。

#10
自動車メーカー7社「半導体調達力」が弱いのは?SUBARUに続き買い負け地獄に陥った“2社”
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
世界の半導体市場が4年ぶりに縮小するにもかかわらず、ホンダやトヨタ自動車系のデンソーが半導体調達の安定化を図る協業が相次いでいる。大手自動車メーカーにとって、半導体不足が自動車の大減産を招いたショックは大きく、「購買部門の弱体化」は自動車メーカーの存亡を左右するレベルにまで達しているのだ。それでは、半導体を筆頭とする部品調達力の強化が急務となっているのはどの自動車メーカーなのか。本稿では、買い負け地獄に陥った自動車メーカーを炙り出す。

水素は「もう終わった」のか?燃料電池車が先行き不透明に見えてしまっている理由
桃田健史
一時は「究極のエコカー」ともてはやされた燃料電池車(FCV)だが、最近は新型電気自動車(EV)の発売が相次ぐ中、その存在感が薄れている印象がある。課題は、燃料電池車に対する供給側と消費者との「意識のギャップ」の解消だ。

トヨタ、ホンダ、日産…自動車5社「半導体不足」続くも月次販売台数に明暗
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,山出暁子
コロナ禍の収束を待たずに、今度は資源・資材の高騰や円安が企業を揺さぶっている。上場100社超、30業界を上回る月次業績データをつぶさに見ると、企業の再起力において明暗がはっきりと分かれている。前年同期と比べた月次業績データの推移から、6つの天気図で各社がいま置かれた状況を明らかにする。今回は、2022年10~12月度の自動車編だ。

中古車が新車より高い「ロレックス化」、価格高止まりの恐れがあるワケ
鈴木貴博
国内中古車市場が異常事態です。国内中古車価格は過去最高水準に到達し、一部の車種で中古車価格が新車価格を上回る「逆転現象」が起きているのです。新車の供給不足は約2年後まで続くといわれています。しかし、実は2年たっても中古車相場は高止まりするかもしれません。その理由をお話ししましょう。

マツダ「CX-60」FR・3.3L直6ディーゼルマイルドハイブリッド搭載【試乗記】
CAR and DRIVER
4種類のパワートレーンが揃う計画が明らかにされているが、今回ドライブしたのはディーゼル+マイルドハイブリッドのe-SKYACTIV Dで、グレード名はXD-HYBRIDとなる。

#28
23年はテスラが首位に立ち「EV大衆化元年」に!トヨタ、ホンダら日系7社の反撃策は?
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
2023年の自動車業界は歴史的な局面を迎えることになりそうだ。米テスラの電気自動車(EV)、「モデルY」が、2023年の年間販売台数で世界首位に立つ公算が高まっているのだ。23年がEV大衆化元年といえる三つの根拠を示すと共に、EVに出遅れ気味の日系7社の「反撃策」に迫る。

#4
第二のマレリも!?自動車業界109社の倒産危険度が5軸チャートで一目瞭然!金利上昇、インフレに弱いのは?
ダイヤモンド編集部,清水理裕
自動車部品大手のマレリホールディングスが今年6月に倒産したことは、自動車業界の苦境を強く印象付けた。半導体不足など、厳しい状況は依然続く。来年、第二のマレリは現れるのか?金利上昇、インフレ耐久度といった独自の試算に加え、身の丈を超えた有利子負債を抱え込んでいないかどうかなど、五つのチェックポイントで自動車業界を総合的に評価。五角形のレーダーチャートで、その診断結果を分かりやすく見せた。なお、この記事は無料公開(要会員登録)。#3の完全版ランキングとセットで読むと、よりグラフィカルに自動車業界で危険な会社の状況をつかむことができる。

マツダ・ロードスター、乗るたびにスポーツカーは素晴らしいと実感する傑作【試乗記】
CAR and DRIVER
ロードスター(ND型)、2015年の登場ながら、ぜんぜん古さを感じない。デビューから7年経過したクルマがなぜ注目を集めるのだろう。それは2021年末に現行ND型の歴史において注目すべき動きがあったことも大きい。最大のポイントは、KPC(キネマティック・ポスチャー・コントロール)と呼ぶ新技術の導入だ。KPCは、ロードスターのリアサスペンション特性を活かし、コーナリング時にリア内輪をわずかに制動することでロールを軽減。姿勢を安定させる仕組みだ。

マツダ「CX-60」試乗記、縦置きエンジン・後輪駆動が生み出す乗り味の魅力とは
MEN’S EX ONLINE
近年マツダはスモールとラージ、2つの新世代商品群の開発を進めてきた。スモールの第1弾がマツダ3。そして、ラージの第1弾が今回登場したCX-60だ。その最大の特徴は、縦置きエンジン+後輪駆動プラットフォームであること。仕向地によってパワートレインは異なるが、新開発の6気筒ガソリンエンジン(日本仕様に設定なし)や、直6ディーゼルエンジン、48Vマイルドハイブリッド、PHEVなどを用意する。

マツダが30年ぶりの「高級車市場」再参入、その狙いと対輸入車の勝算とは
佃 義夫
マツダは上級SUV「CX-60」を国内で販売開始した。CX-60は同社が上級車種群と位置付ける「ラージ商品群」の第一弾であり、バブル期以来の「高級車市場」への挑戦となる。

ホンダの韓国LG・米GMとの提携強化が映す、自動車業界「大変革」の衝撃
真壁昭夫
ホンダは、米国のGMと韓国のLGグループとアライアンスを組んで、「100年に1度」と呼ばれる自動車産業の大変革に対応しようとしている。背景にある「CASE」のインパクトは大きい。バッテリー調達能力の向上、自動運転技術などソフトウエア開発力の強化、搭載点数の増える車載用の半導体開発のために、世界の大手自動車メーカーは合従連衡や異業種との提携を強化しなければならない。
